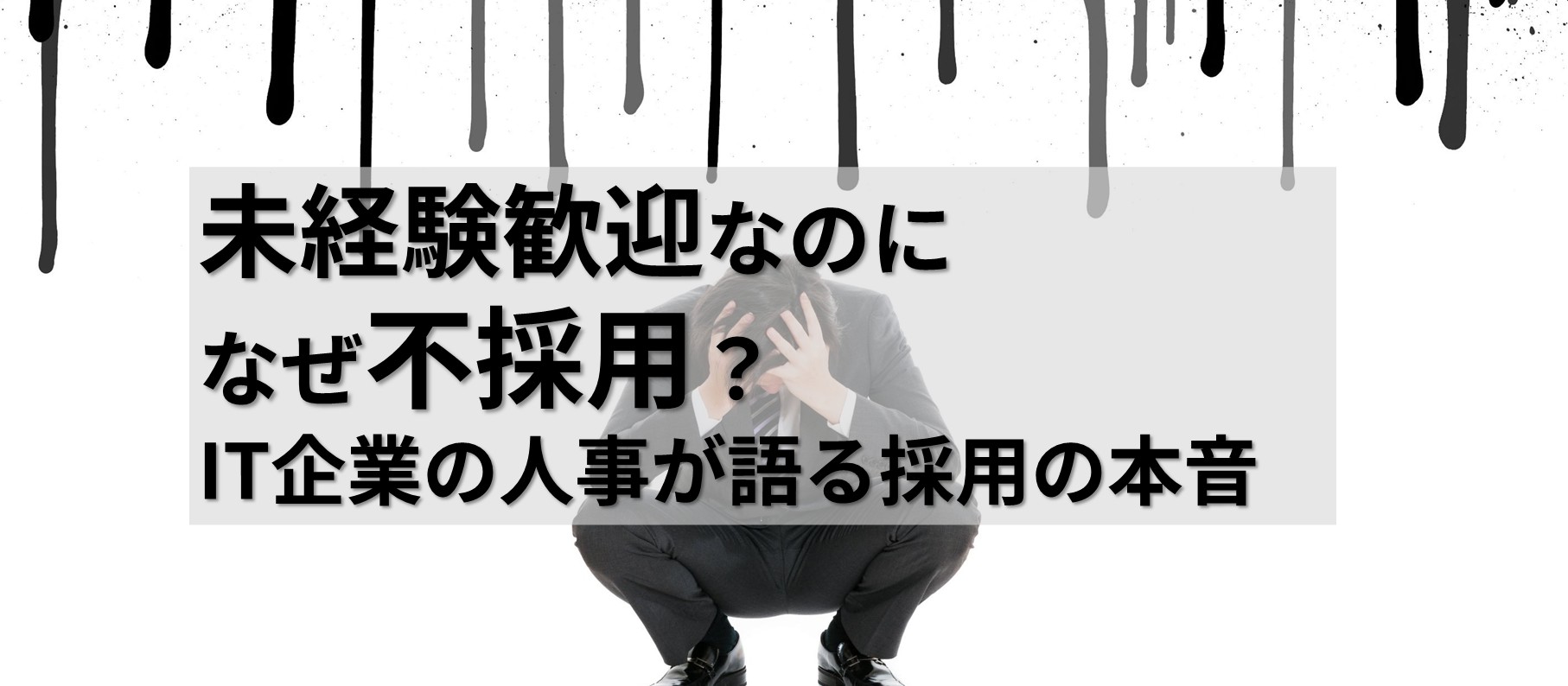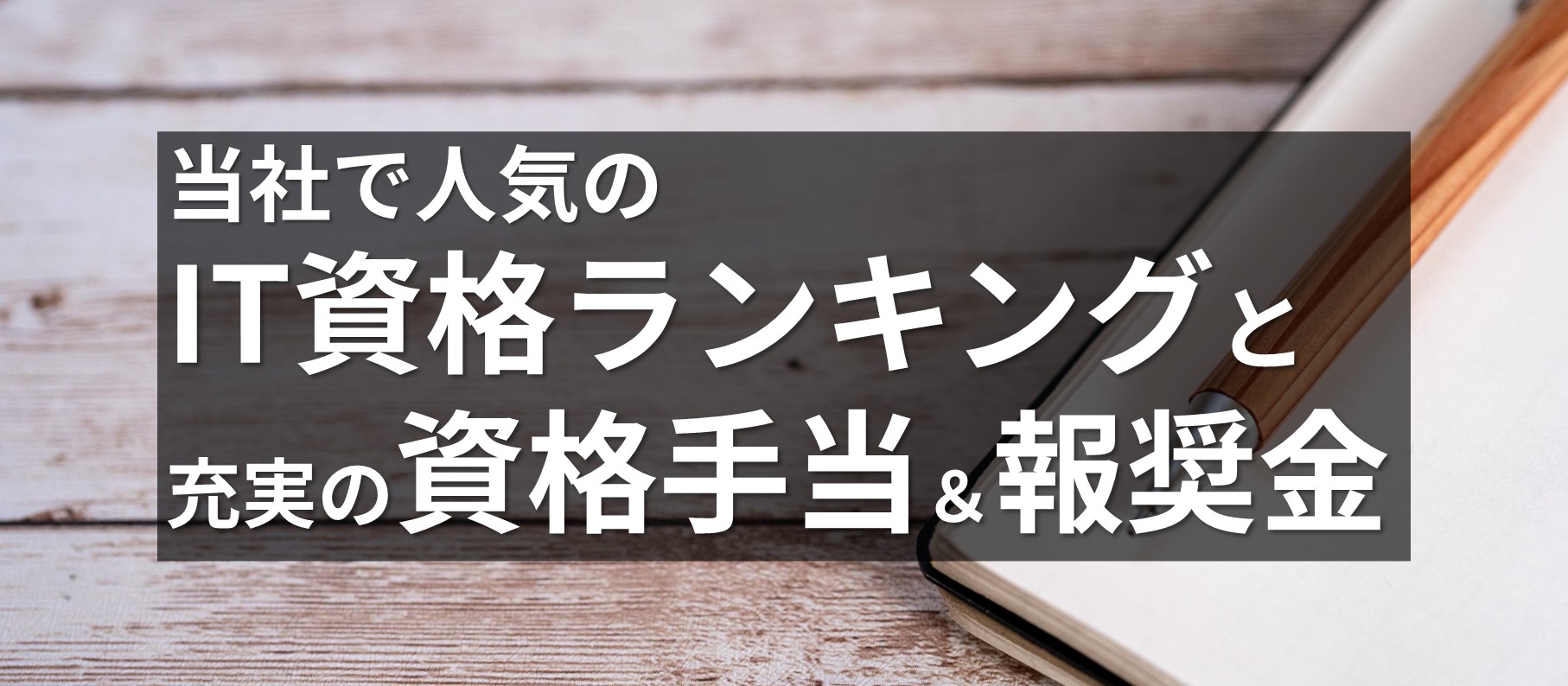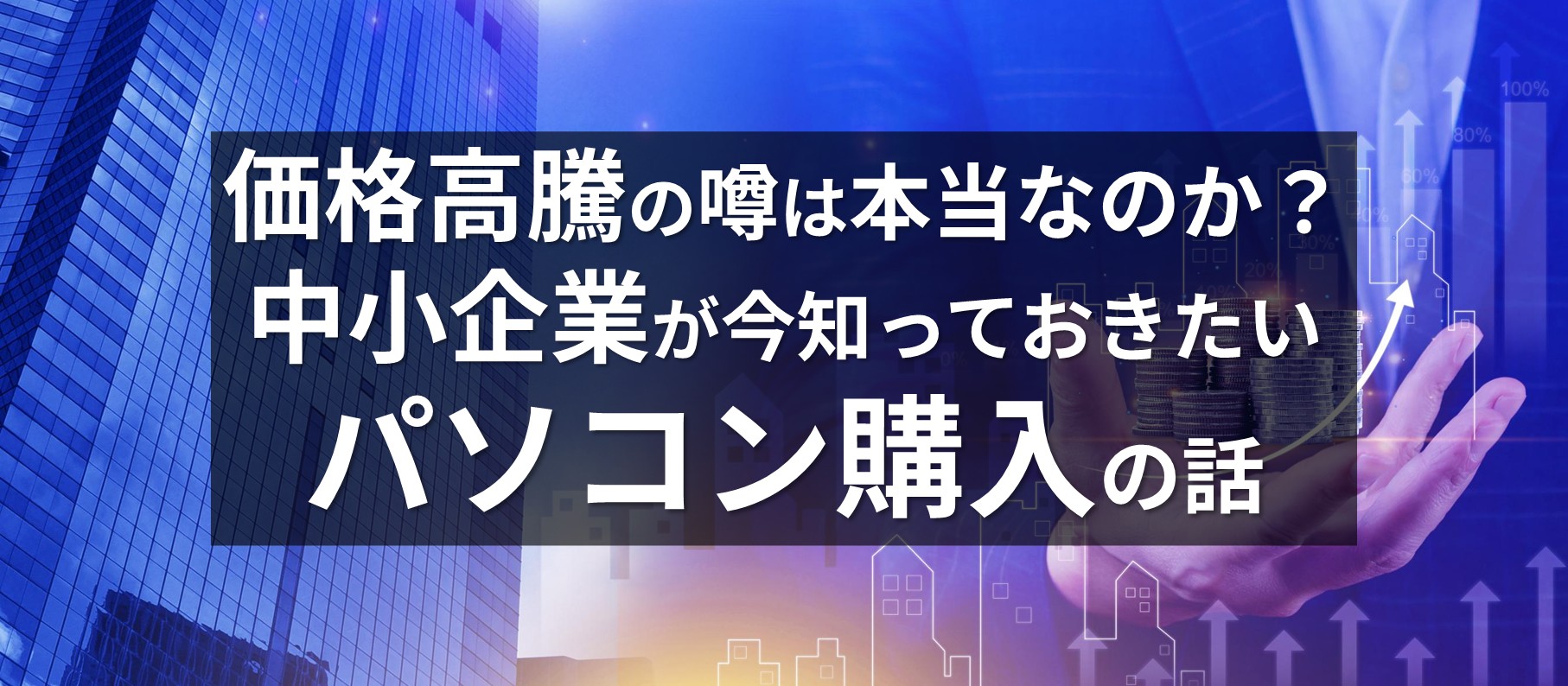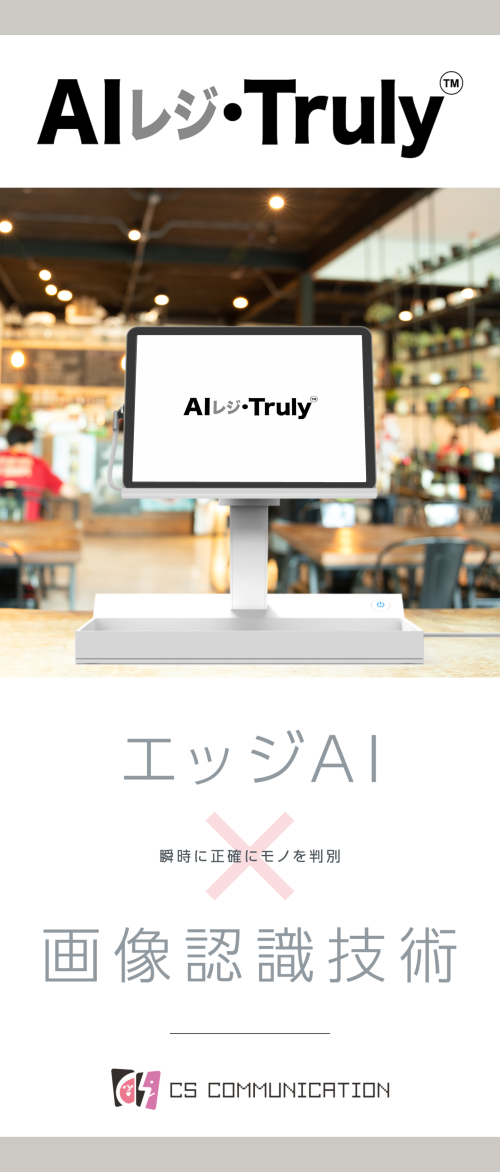「運用」ってどんな仕事?未経験エンジニアでもわかる超やさしい解説
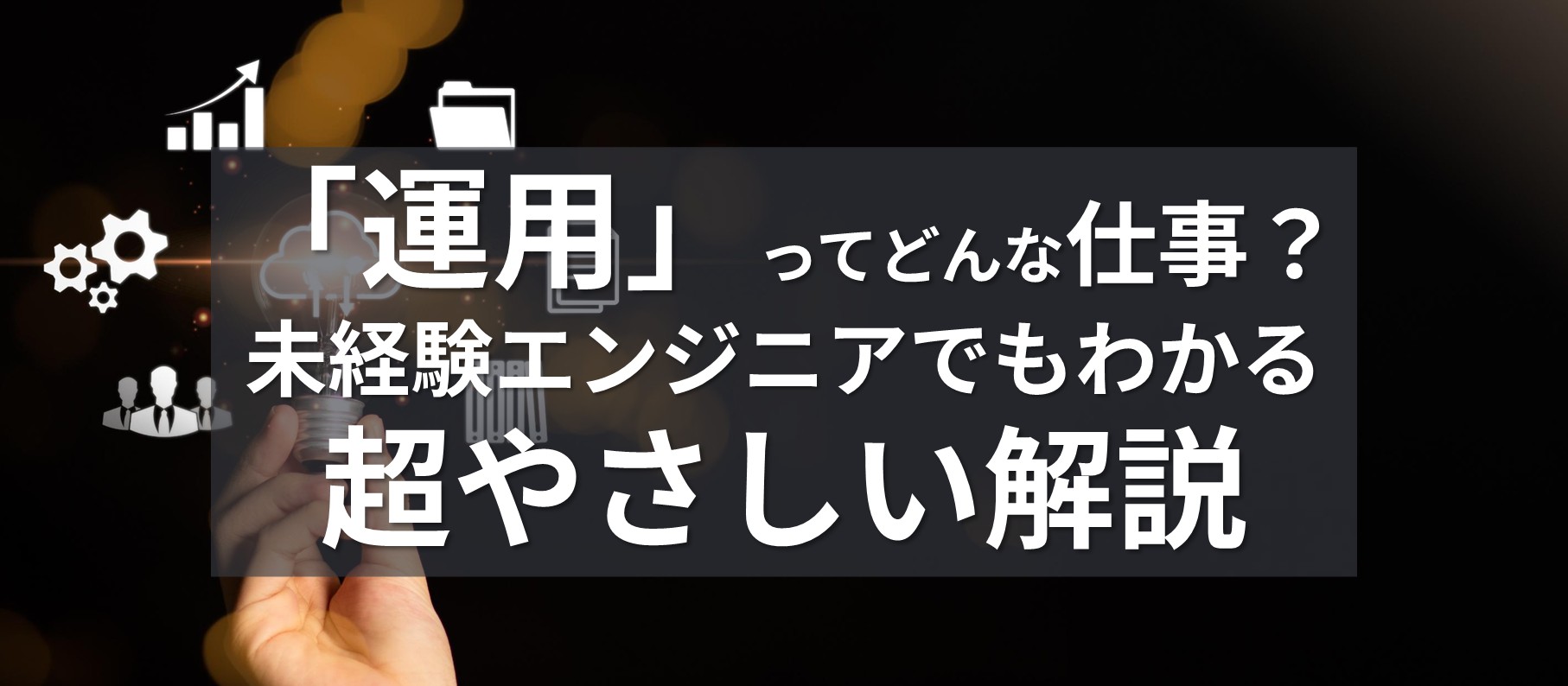
と求人記事に書いてあるのを見て、「そもそも“運用”ってなに??」と思ったことはありませんか?
開発や構築は“作る仕事”なので想像しやすいのですが、運用は“使われ続ける裏側”のため一般的に見えにくく、想像しにくいものです。
その結果、多くの未経験者が「運用って結局なにをするの?」という疑問を抱きます。
しかし実は、企業にとって最も重要で、システムの価値を左右するのが運用です。
本記事では、運用をまず言葉で整理し、さらに“ビルの建築と管理”で例えることで、誰でも一発で理解できるように解説します。

「運用」がなかったらどうなる?社会維持の仕事
IT業界で「運用」の仕事を一言で説明すると、「お客様の利用・提供するITの仕組みを、常に正常に動く状態へ維持する仕事」と言えます。
企業が使っているシステムは、仕事が行われている毎日・24時間どこかの現場で、社員やお客さんがアクセスし続けています。
たとえば社内の勤怠システム、予約サイト、ネットショップ、業務アプリ、銀行の口座管理など、人の生活やビジネスを支える仕組みは、すべて裏側で絶えず動き続けています。
運用エンジニアの仕事は、こうした 「誰かが使っているシステム」を対象に、いつでも正常に動くように見守り、異常があれば気づき、必要に応じて対処することです。
もし運用が機能しなくなると、システムに問題が発生した際に正常へ戻せず、企業や利用者が使っているITの仕組みはそのまま停止してしまいます。
社員は勤怠も入力できず、メールも送れず、業務が完全に止まります。
予約サイトやネットショップが動かなくなれば、注文も支払いもできず、企業の売上はその瞬間からゼロになります。
医療機関なら受け付けが滞り、交通機関なら運行管理が乱れ、金融サービスなら振込や決済ができなくなるかもしれません。
ITの仕組みは、今や生活やビジネスの“前提”として存在しているため、一つのシステムが止まるだけで想像以上に広い範囲へ影響が広がります。
つまり運用とは、「つねにどこかで動いている、誰かが使っているITシステムを、安全に、問題なく使い続けられるように管理する仕事」に他なりません。
システムを作るのは開発や構築ですが、作られたシステムを“毎日使える状態に保つ”のは運用の役割です。
ITプロジェクトの流れをビル建設と比較して「運用」を解説
ITの運用は運用は言葉だけでは抽象的に感じやすいため、ここからは実際の建物を例にして、「作る」と「支える」の違いを具体的に見ていきましょう。
今回は「ビル(イベントホール)」を建設するケースと、「システム(予約サイト)」を作成するケースを比較して、設計→構築→開発→運用→保守といったITシステムの流れを説明します。
● 設計
建物を建てるとき、建築士が図面を引き、どんな広さの部屋を作り、どれだけの人が利用できるか、どんな設備を入れるかを決めていきます。
これはITでいえば、誰が使い、どんな機能が必要で、どれくらいのアクセスが想定されるのかといった“設計”にあたります。
ビル:「何人が使う?」「部屋はいくつ?」「ホールは何席?」など、利用目的に応じて建築士が設計する。
システム:「誰が使う?」「どんな予約項目?」「決済は必要?」など、要件に応じてシステムの設計をする。
● 構築
設計に基づいて実際に建物を建てていきますが、まずは建物そのものを成り立たせるための“土台づくり”が必要になります。
電気や水道の配管を通して、空調のダクトを入れ、通信回線を引き、建物全体を安全に動かす仕組みを整えるところです。
ITの世界では、サーバーを準備し、ネットワークを構築し、データベースを用意して、アプリケーションが動ける環境を作る「インフラ構築」がこれにあたります。
ビル:骨組みや配線を通し、電気・水道・空調の基礎設備を整える。
システム:サーバー・ネットワーク・データベースといった“裏側の環境”を作り、アプリが動く土台を整える。
● 開発
土台や外観、電気・水道などの準備が完成したら、今度は内装工事が始まります。
ホール内装を作り、会議室を区切り、照明や空調、トイレなどの設備を取り付けていく工程です。
ITシステムなら、利用者が触れる部分、ログイン画面、予約入力画面、空き状況の検索画面などをプログラミングで形にしていく段階に相当します。
ビル:内装業者が部屋を作り、設備業者が照明・空調・水回りを取り付けていく。
システム:エンジニアが画面や機能(ログイン/予約登録/空き状況検索など)をプログラミングする。
● 運用
ここまで整って初めて、施設が利用できるようになります。
しかし、建った瞬間がゴールではありません。
毎日イベントホールで催しが行われ、多くの設備が常に動き続けます。
空調が正常か、エレベーターに異常はないか、電気や水道がトラブルなく使えるか、利用者からの問い合わせなど、こうした“日々の管理”が欠かせません。
これがITにおける「運用」にあたります。
動き続ける予約サイトも同じです。
サーバーが正常に動いているか、予約データが正しく保存されているか、アクセスが増えて動作が遅くなっていないか、不正なアクセスが混ざっていないかを確かめる必要があります。
利用者から「予約完了メールが届かない」「ログインできない」と問い合わせがあれば状況を確認し、原因を探し、元の状態へ戻します。
複合施設の“毎日の管理”と同じように、ITシステムも誰かが使う限り、裏側で支える役割が必要なのです。
ビル:毎日の点検、空調温度の管理、エレベーターの状態確認、防犯カメラの監視、利用者の問い合わせ対応。
システム:予約サイトが止まっていないかを監視し、エラーがあれば原因を調べ、必要に応じて復旧し、問い合わせに答える。
● 保守
そして、もし設備が壊れたり、予期せぬトラブルが起きた場合は、修理の出番です。
建物でいえば水漏れやエレベーター故障、ITならシステム停止やデータ不具合の復旧がここにあたります。
運用が“毎日の見守り”なら、保守は“異常が起きたときの修理”です。
ビル:水漏れやエレベーター故障など、異常時の修理対応。
システム:システム停止やデータ不具合の復旧、バグ修正、壊れた機器の交換。
こうして並べてみると、ビルの管理とITシステムの管理は、とてもよく似ている構造をしていることがわかります。
建てたあとに利用者が日々安心して使える状態を保つこと──これこそが運用の本質であり、多くの人が“当たり前”だと思っている部分を裏側で支えている仕事なのです。
運用の仕事が持つ魅力と、未経験との相性
運用の仕事は、派手さこそありませんが、ITの世界では欠かせない役割です。
複合施設の管理が日々の安心を支えるように、ITシステムの運用も、企業や利用者が不便を感じずに過ごせる“当たり前”を裏側で守っています。
この“当たり前を守る”という視点そのものが、運用の魅力のひとつです。
そして運用は、未経験者にとって最も入りやすいIT職種のひとつでもあります。
いきなり高度な技術を求められるわけではなく、まずは手順に沿って状況を確認し、落ち着いて判断する力があれば問題ありません。
むしろ、丁寧さや気づき、責任感といった“人としての基礎力”が評価される仕事です。
さらに、運用の現場ではシステムの構造、ネットワークの流れ、データの扱われ方など、ITの基礎を自然と身につけることになります。
未経験でIT業界に入った人が「最初のステップ」として選ぶ理由はここにあります。
しかし、中には「自分は最初からプログラミングの仕事だけやりたい」という方や、「設計の段階でお客様にもっとよいシステムを提案したい」と考える方もいるでしょう。
もちろん、自分の目指すキャリアに向かって進むこと自体はとても良いことです。
ただ、お客様が本当に求めていることを経験から理解しているエンジニアと、頭の中の知識だけで判断してしまうエンジニアでは、どちらが喜ばれるシステムを作れるでしょうか。
システムがどのように使われ、どこでつまずき、どんなトラブルが起こりやすいのか。
こうした現場の“事実”は、運用や保守といった下流工程に触れなければ見えてきません。
特に、AIが発達し、開発や構築が以前より容易になっていくこれからの時代においては、技術そのものより、むしろ 「現場の理解」や「利用者の困りごとを正確に把握できる力」 が価値になります。
ボタンを押せばコードが生成される世界では、実際の利用場面を深く理解している人ほど、的確に問題を捉え、より良い設計や提案につなげることができます。
AIはコードを書くことはできますが、“人がどこで困っているのか”、“どんな運用ならミスが起きないのか”、“どの使い方がビジネスにとって危険なのか”といった“現場の感覚”までは代替できません。
だからこそ、運用や保守の経験は、将来プログラミングや設計の仕事に進むための大きな財産になります。
運用から目指せる次のキャリア
将来性という面でも、運用は非常に強い道です。
クラウド化やAI化が進んでも、システムが動き続ける限り“運用”の仕事がなくなることはありません。
むしろ、クラウド化によってシステムは複雑化し、監視や調整の重要性は増しています。
自動化やAIが利用される場面も増えていますが、その自動化された仕組み自体を監視し、判断し、必要な調整を行うのも人間です。
こうした運用の経験を積んだ後にはどんなキャリアが広がるのでしょうか。
たとえば、社内のIT環境を整える情シス(情報システム部門)に進む人もいれば、サーバーやネットワークを専門的に構築するインフラエンジニアへ進む人もいます。
クラウドの知識を深めてAWSやAzureを扱うクラウドエンジニアになる道もありますし、システムの安定性を高めることを専門とするSRE(Site Reliability Engineering)の領域に挑戦する人もいます。
また、運用を通じて身についた“利用者視点”を活かし、システムエンジニアとして要件定義や設計といった上流工程へ進むことも珍しくありません。
つまり運用は、ITの世界でキャリアを広げるための土台となる経験を積める場所とも言えます。
土台となる経験を積んでおくことは、AI時代におけるエンジニアの生存戦略と言っても過言ではありませんので、長期的なキャリアを考える上でも非常に有効な選択でしょう。
今回は「運用」という仕事について説明をしてきました。
運用は“経験がないとできない仕事”ではありません。
むしろ、丁寧に取り組む姿勢が評価されるため、最初のキャリアとして適している仕事です。
未経験からITエンジニアを目指す方が、安心して運用業務に従事できるようになればと思っています。