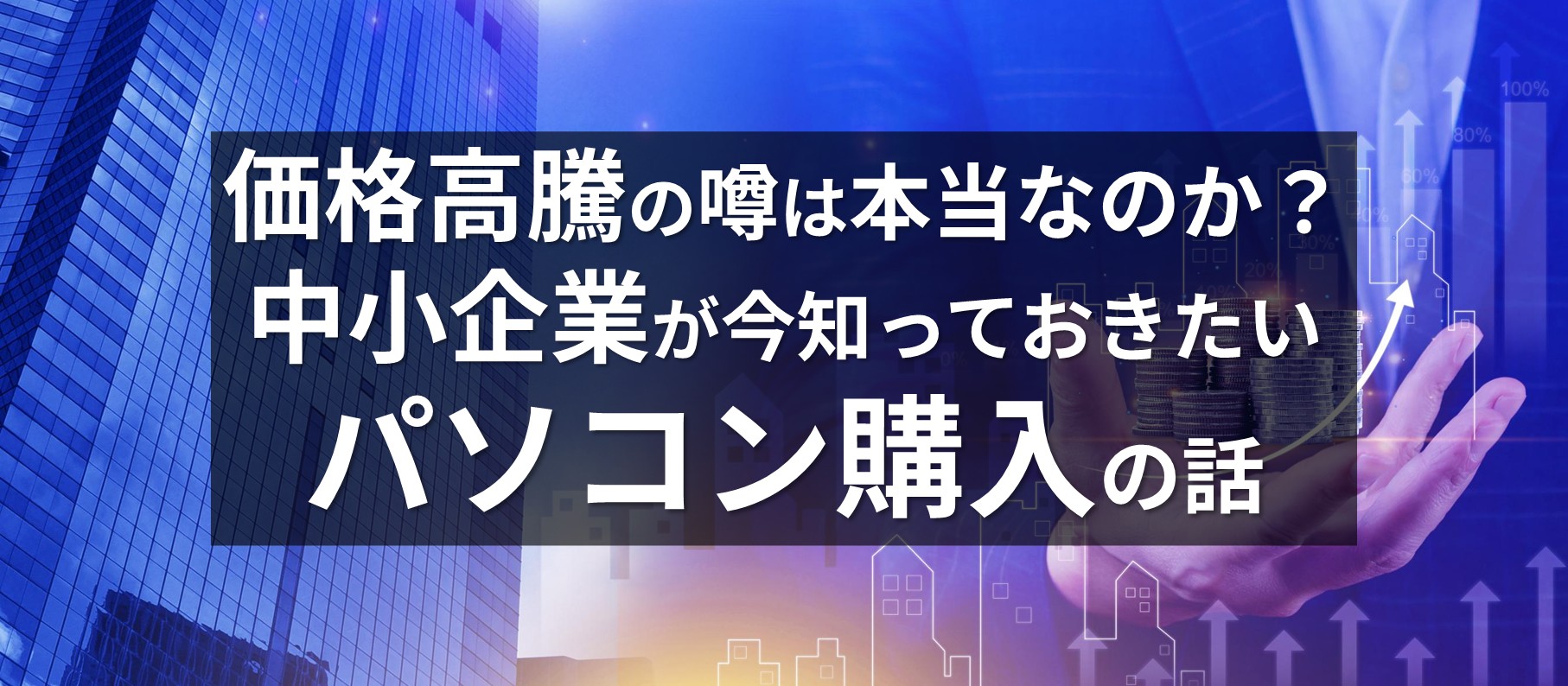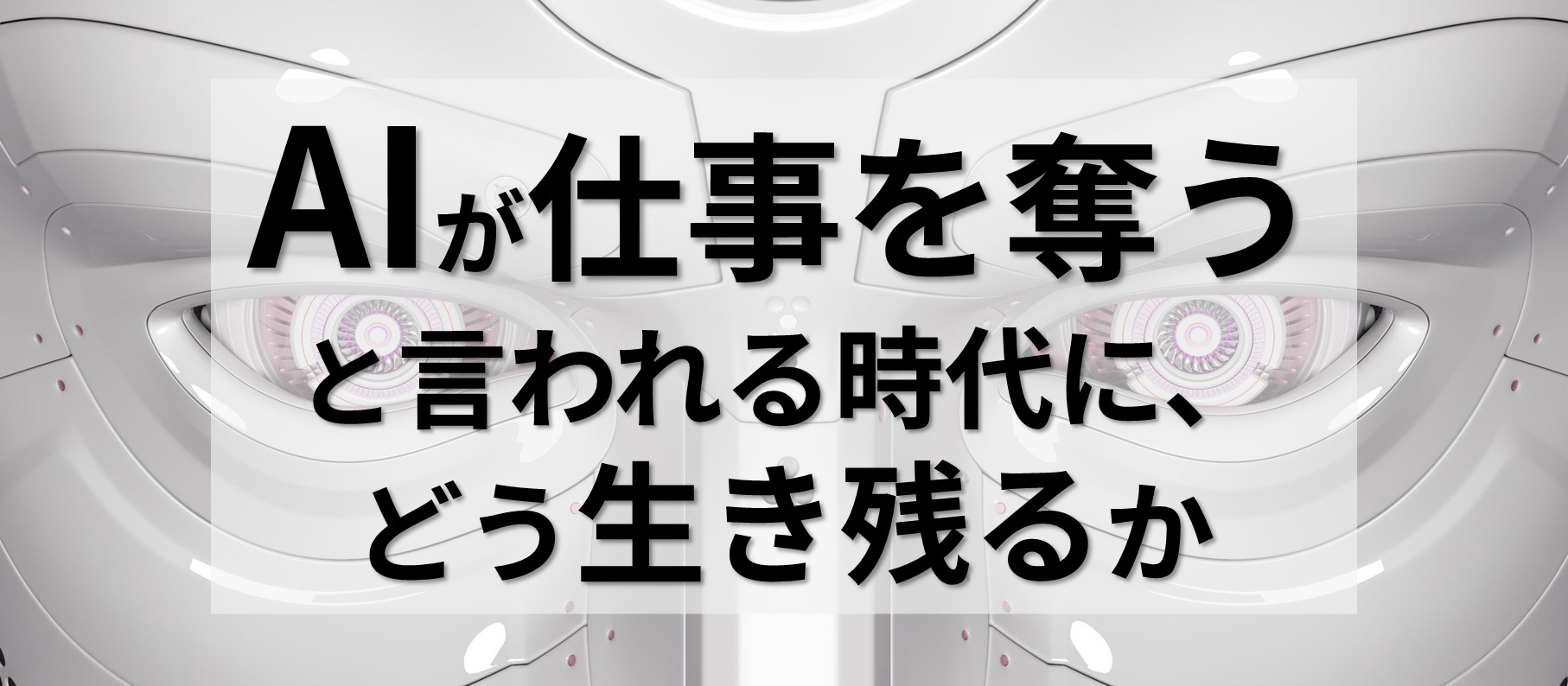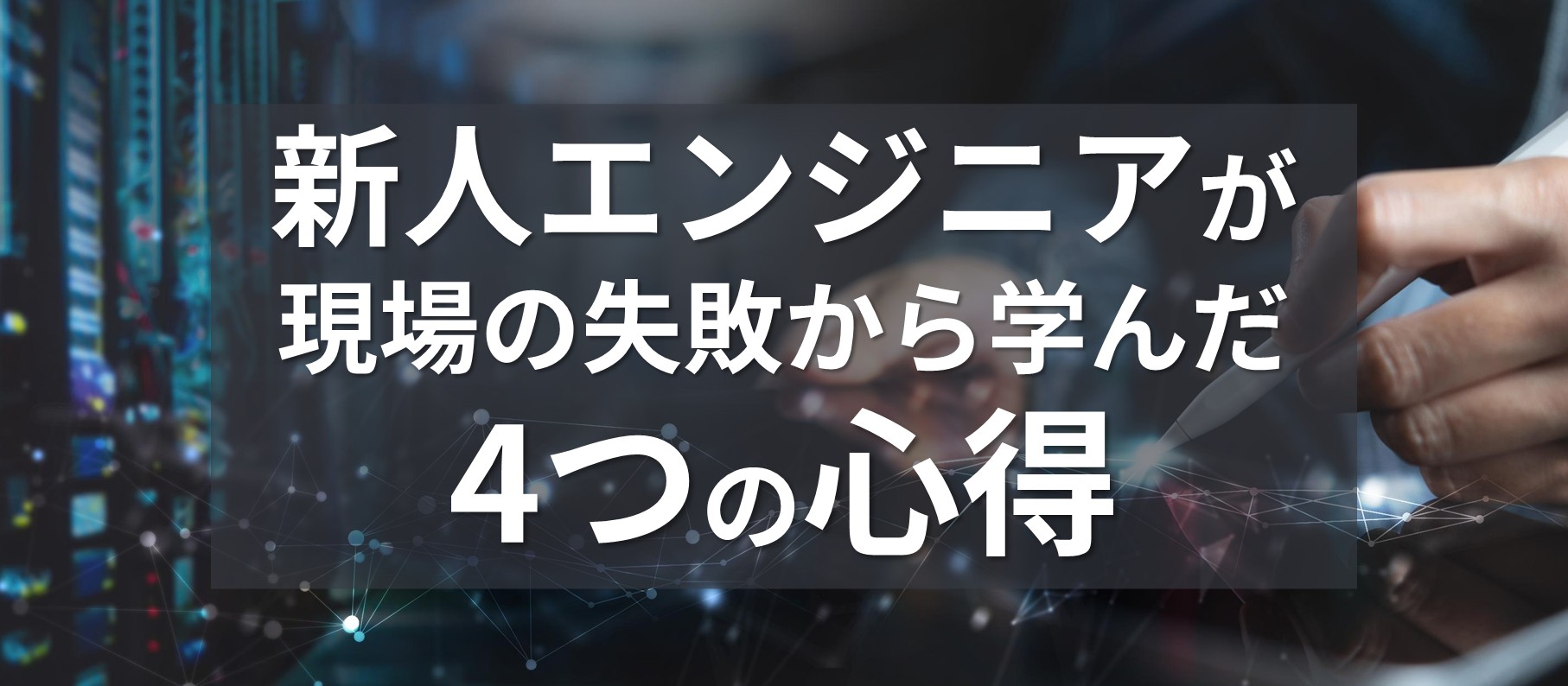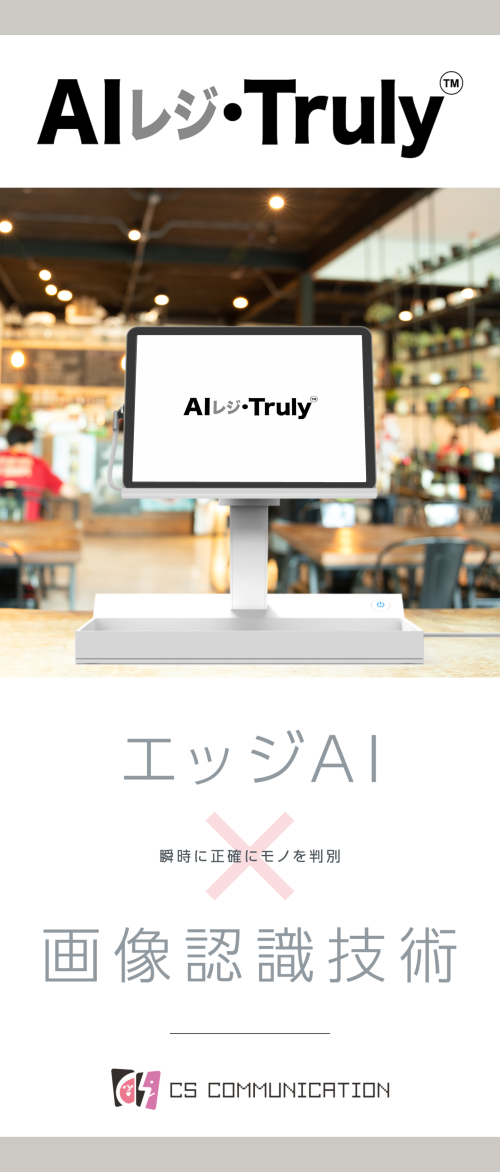『IT初心者向け解説 第1回:サーバ編』

はじめまして、ロニーです!
こんにちは、ロニーです。
シーエスコミュニケーションに未経験で入社し、
現在はネットワークエンジニアとして現場を経験しながら業務に励んでいます!
普段の業務などで新しく学んでいっている知識・経験をシェアすべく、
今回から不定期で技術的な内容をブログに投稿をしていこうと思います。
初心者の方向けの基本的な内容が多くなりますが、
未経験の方、専門外の方にも分かりやすく解説したいと思いますので、
一緒に勉強していきましょう!
IT用語は語尾がerで終わる単語、
つまりカタカナだと「ー(伸ばし棒)」で終わる単語が多いです。
一般的に語尾の伸ばし棒は省略することが多いので、僕の投稿ではそれに準じます。
以降、例えば「サーバ」 = 「サーバー」と捉えてください。
サーバって・・・なに??

さて、第1回は、「サーバとは何か」です。
IT業界に関わる仕事をしていないとあまり関わることのない「サーバ」ですが、
ネットワークにしても、
Webにしても、
アプリケーションにしても、
IT業界で仕事をする上でサーバの理解は必須項目ではないでしょうか。
なので基礎的な内容となりますが、まずは
「サーバとは何か」
というテーマでいってみましょう。
一般的な定義から抜粋すると、サーバとは、
「ネットワーク上のコンピュータの中で、他のコンピュータ(クライアント)から要求や指示を受け、情報や処理結果を返す役割を持つコンピュータやソフトウェアのこと。」
です。
簡単に言うと
「いろいろな機能を提供(serve)するコンピュータやソフト」
なわけですが、
でも、これだけだと、
「普通のパソコンも色んな機能を提供するじゃん?どう違うの?」
という疑問が浮かんできますよね?
普段使っているパソコンとサーバの大きな違いは、
「端末外部の」「多くの」ユーザに、「専門的に」機能を提供しているか否か、です。
機能を提供する側のサーバから見て、ユーザが直接操作しているパソコンは外部の「クライアント」と呼ばれます。
ユーザがクライアント端末(パソコンなど)からアプリケーションを通してサーバになんらかのリクエストを送り、
受けたサーバが応答して情報や処理結果を送ります。
サーバは提供するその機能の種類によって変わります。
Webページを提唱していれば、Webサーバとなったり、
アプリケーションを提供していれば、アプリケーションサーバとなったり、
メールを提供していれば、メールサーバとなったりします。
物理的なサーバそれ自体はただのコンピュータの箱、大きな計算機みたいなもので、
パソコンと作りは大きく変わりません。
その物理サーバに、持たせたい機能に応じたミドルウェア(また別の機会で説明します)をインストールすることで、
色んな種類のサーバとなります。
ポケモンのイーブイみたいですね。

また、1つの物理サーバに別の種類の複数のミドルウェアを搭載することで、
例えばWebサーバとアプリケーションサーバを兼務するサーバとすることもできます。
現在は1つの物理サーバをそのまま1つのサーバとして使うことよりも、
物理サーバの上に複数の仮想サーバを立てて使うことが多いのですが、それはまた別途話題に上げましょう。
ちなみに普段使っているパソコンをサーバ代わりにすることも可能です。
なんでサーバが必要なの?

ではなぜパソコンだけで完結させるのではなく、
わざわざ「サーバ」を使うのか?
これは、現代人のほとんどが意識せずに利用している、
Webサーバを考えるとわかります。
普段ネット検索して見ているWebページは、どこかの誰かのWebサーバが保管しているデータにアクセスし、
その情報を送ってもらうことで自分のクライアント端末に表示されています。
もしそのリクエストを処理し、情報を送り返しているのが個人のパソコンだったとしたら、
そのパソコンが破損したりフリーズしたりしたら情報を送り返せません。
人に寄りますが、個人のパソコン上には様々なアプリが動いていて、それぞれのプログラムを順番にさばいています。
もし大勢が見るWebサイトの情報を管理しているパソコンで、管理者が例えばゲームなどをしていて負荷をかけたら、閲覧しているユーザへスムーズに情報を提供できません。
なので、サーバとして使うコンピュータには、その業務に専門に動いてもらった方が、
安定的でよいパフォーマンスを出してもらえます。
その昔、何にでも使える、高価でデカイ汎用的なコンピュータがありました。
そのコンピュータを使うために、ユーザはアクセス機能だけを持ったクライアント端末を使っていました。
やがて技術革新していく中でハードウェアが小さくなり、データの転送速度も速くなったことで、
そのクライアント端末自体にもあらゆる機能を持たせられるようになりました。
クライアント端末は、個々人のユーザが日々使いやすいように色々な機能を少しずつ搭載したコンピュータとなりました。
これがパーソナルコンピュータ(=パソコン)。
一方、専門的な機能を処理・管理することに集中し、大勢のユーザに機能を提供していた大本のコンピュータの方からサーバが生まれました。
こういった歴史的経緯を考えれば、
パソコンとサーバの使い分けに納得がいきます。
今回のまとめ!
ここまでの説明を踏まえると、冒頭の定義、
サーバとは、
「ネットワーク上のコンピュータの中で、他のコンピュータ(クライアント)から要求や指示を受け、情報や処理結果を返す役割を持つコンピュータやソフトウェアのこと。」
である。
が理解できると思います。
機能を受ける側のユーザから一歩踏み込んで、
Webサイトを管理する、
アプリを作る、
メール機能を設定する、
というような業務に関わったときに、サーバに触れることになります。
きっと誰しも最初は
「さささサーバってなんだ…???!!!魚??」
と恐怖に身が打ち震えるものと思いますが、
一度触れてしまえば決して難解で意味不明なモノではないので、身構える必要はありません。
サーバを立てる方法は色々あるのでぜひ一度調べて試してみてください!
今回は以上!
また次回も一緒にITを学んでいきましょう!