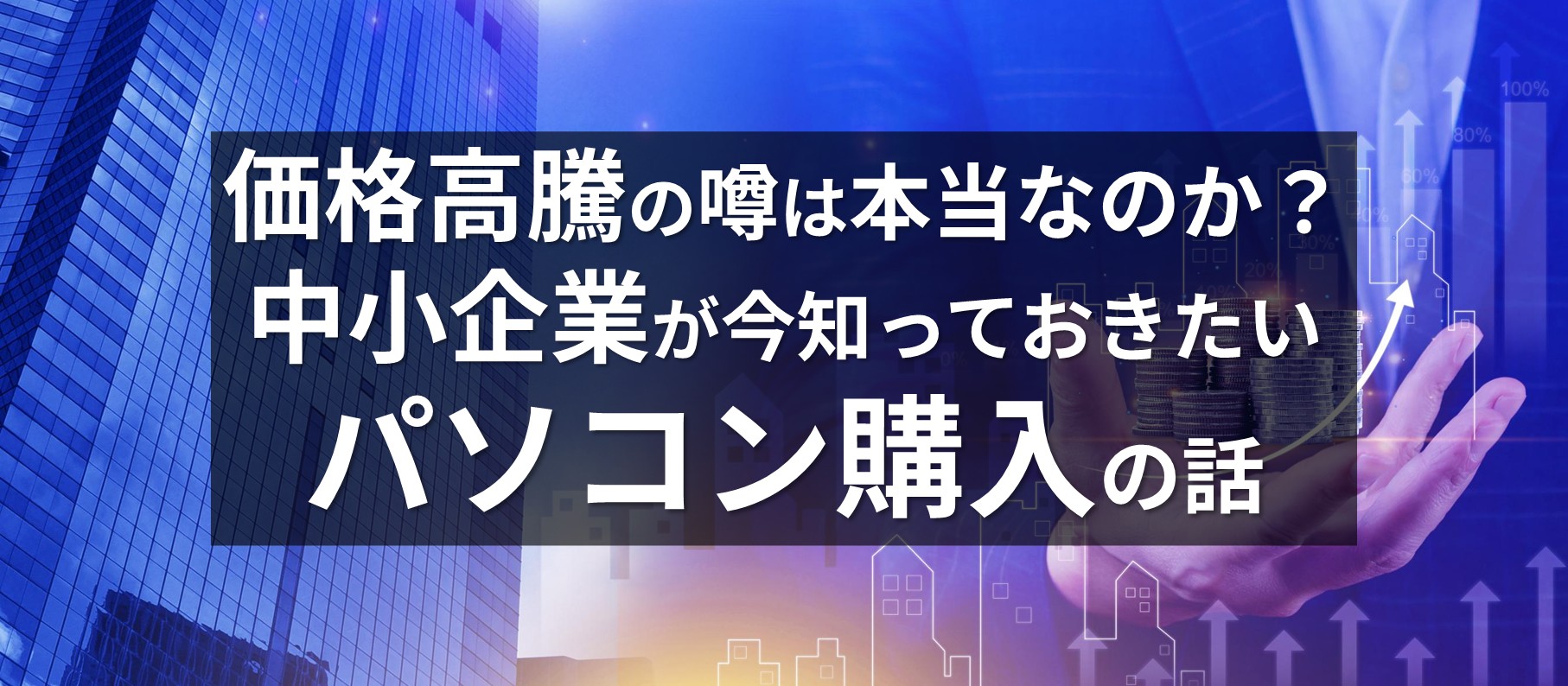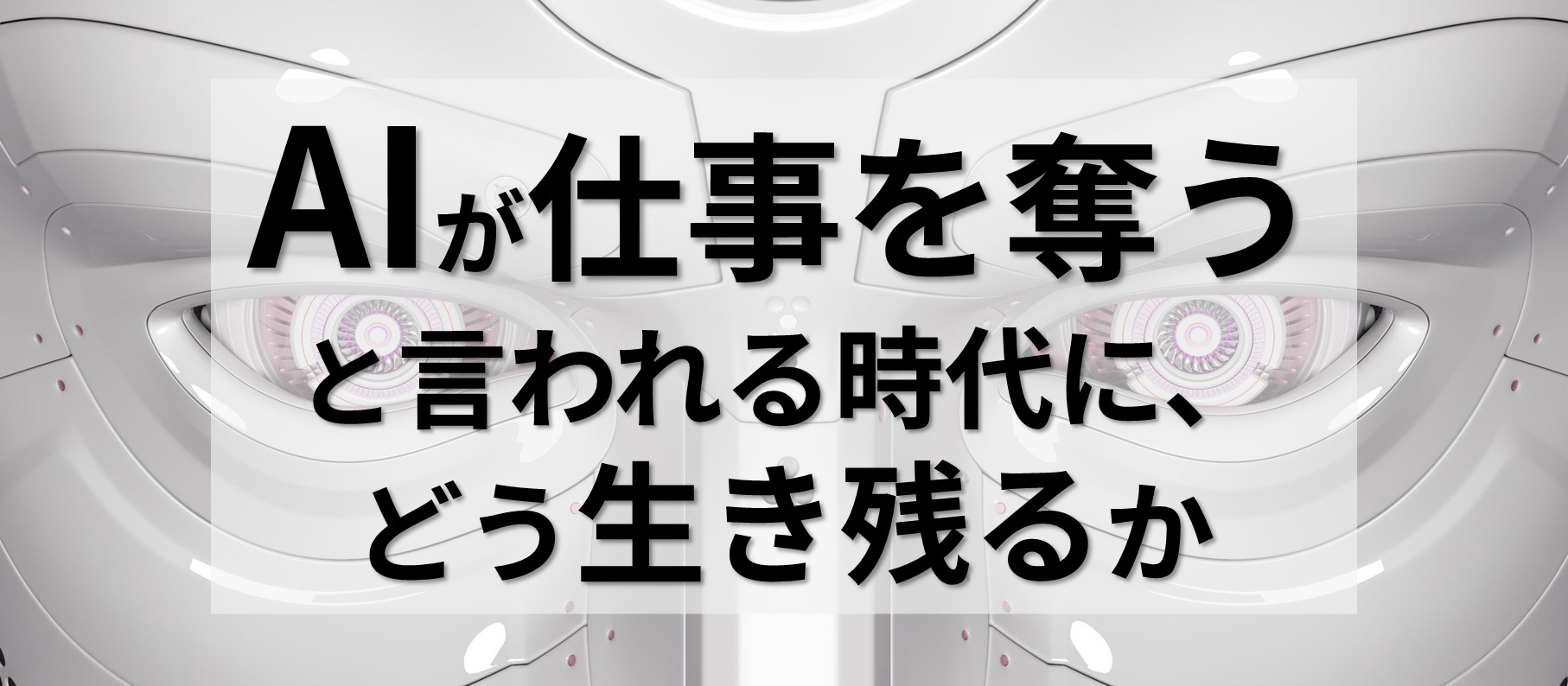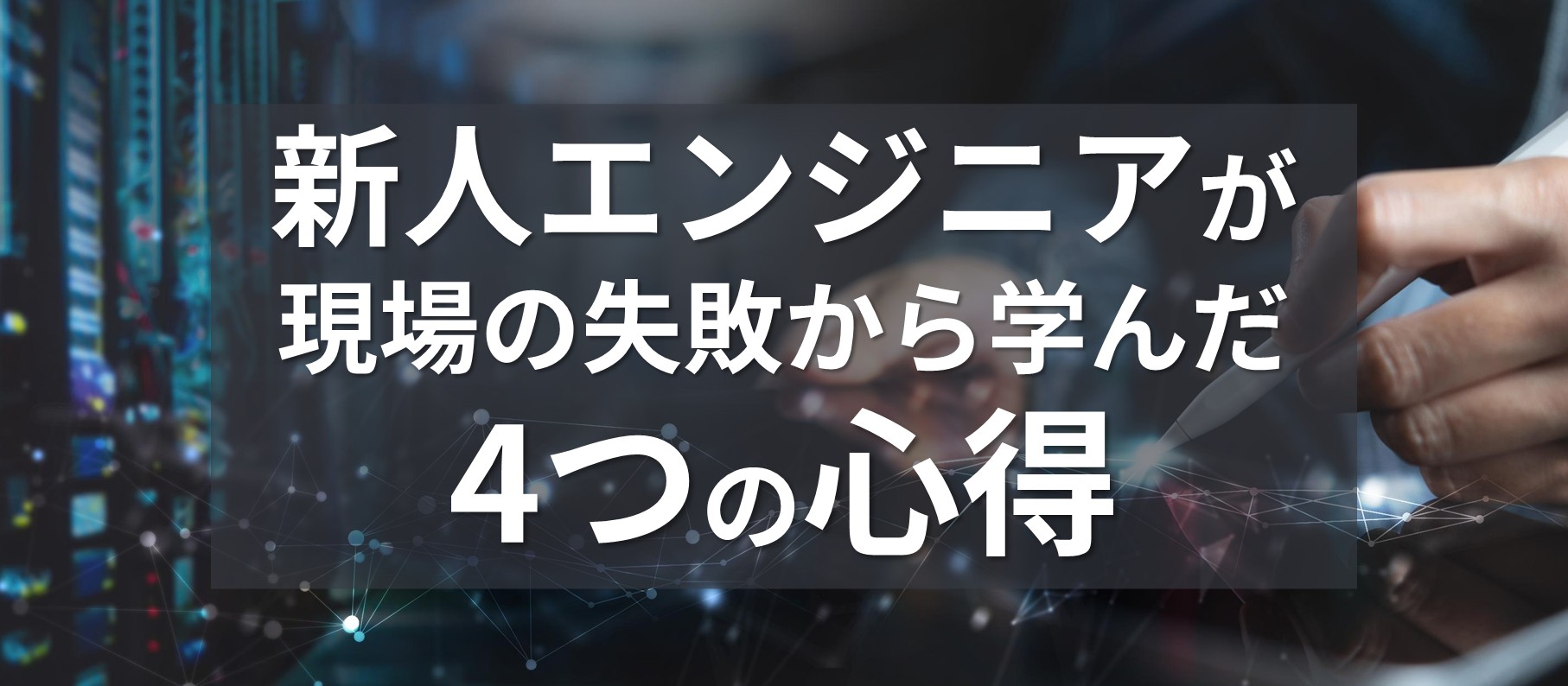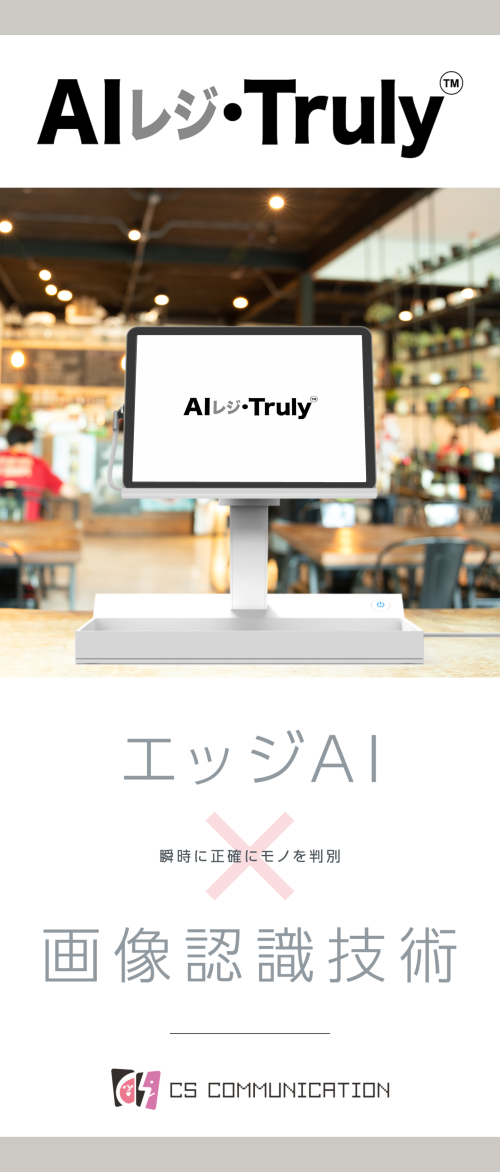ビギナーITエンジニア講座③ サーバーってなんですか?

そんな方も多いのではないでしょうか。 実は、私たちがスマホでゲームをしたり、動画サイトで映画を見たりするとき、その裏でサーバーが情報を届けています。
サーバーを一言であらわすと、必要なデータやサービスをあなたの端末に渡してくれるコンピューターのことです。
今回は身近な例を交えながら、サーバーの基本をどこよりもわかりやすく解説していきます。
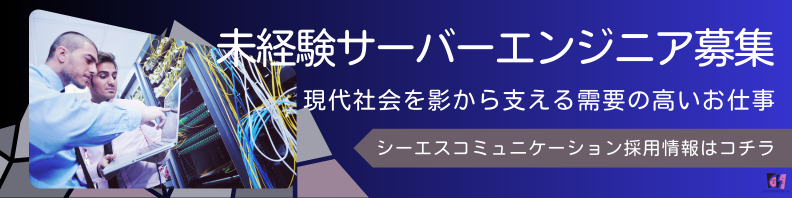
誰もが意識せずに毎日サーバーを使っている現代社会
「サーバー」と聞くと、専門的で難しいイメージを持つ人も多いかもしれません。
しかし実は、私たちの身近な生活の中で常に活躍している存在です。
サーバーとは 「情報やサービスを提供するコンピューター」 のことを指します。
私たちが使うスマホやPCは「クライアント」と呼ばれ、サーバーに対して「この情報をください」とリクエストを送ります。
サーバーはそのリクエストを受け取り、必要な情報を返すことで、初めてサービスが成り立ちます。
たとえば身近な例を挙げてみましょう。
■動画サイト
YouTubeやNetflixなどで映画やアニメを再生するとき、動画ファイルはサーバーに保存されています。
あなたのスマホが「この動画を見たい」とリクエストを送ると、サーバーが動画を配信してくれます。
■オンラインゲーム
ゲームの世界でキャラクターを動かしたりスコアを更新したり、課金してガチャを引く際も、サーバーが情報を管理しています。
あなたがキャラクターを動かすと、その情報はサーバーに送られ、他のプレイヤーの画面にも反映されます。
この仕組みのおかげで、遠く離れた友達とも同じゲーム空間で協力したり競争したりすることができます。
■メールやSNS
メールやLINE、InstagramなどのSNSで送受信する情報もサーバーを通じてやり取りされます。
サーバーがデータを保存し、必要なときに届けたり、投稿を相手の画面に表示させたりする役割を果たしています。
サーバーの基本的な仕組みは「要求と応答」
このように、サーバーとクライアントは 「要求と応答のやり取り」 によって成り立っています。
「クライアントがリクエストを送り、サーバーが応答する」この仕組みを理解することで、ネットワークを利用したサービスの基本構造が見えてきます。
現実のサーバーは、基本の一対一のやり取りだけでなく、同時に何百、何千ものクライアントからのリクエストを処理しています。
たとえば、動画サイトでは数千人が同じ映画を同時に視聴することがありますし、オンラインゲームでは何百人ものプレイヤーがリアルタイムでゲームの世界に参加しています。
また、メールやSNSでは多くの人が同時にメッセージを送受信していても、それぞれの情報が正確に届けられます。
サーバーは、一対一のやり取りを基本にしながら、それを大量に同時に処理することで、私たちが日常的に利用するサービスをスムーズに提供しているのです。
こうした普通のパソコンでは処理しきれない大量のデータや、同時に届く複数のリクエストを高速に処理し、正確にクライアントに返すため、サーバーは高性能な専用コンピューターを使って情報を管理しています。
そして、この 高性能なコンピューター自体のことを「サーバー」と呼ぶこともあります。
つまり、サーバーという言葉は、情報を届ける役割としての「仕組み」を指す場合もあれば、そうした専用の機械(ハード)そのものを指す場合もあるのです。
少しややこしいですね。
Webショッピングもサイトへのログインもサーバーのおかげ
サーバーには、扱う情報や提供するサービスの内容によってさまざまな種類があります。
まずは最も身近なものから見ていきましょう。
■Webサーバー
私たちが普段見ているウェブページを表示するためのサーバーです。
あなたがブラウザでサイトを開くと、Webサーバーがそのページの情報を探して送信し、画面に表示してくれます。
ウェブサイトを閲覧する際に欠かせない存在です。
■メールサーバー
メールの送受信を管理するサーバーです。
送信されたメールは一度メールサーバーに届き、そこから受信者の端末に届けられます。
これによって、私たちは離れた場所にいる友達や仕事仲間とスムーズにやり取りができます。
■ファイルサーバー
データを保存・共有するためのサーバーです。
会社やチームで資料や画像、動画などをまとめて管理し、必要なときに誰でも取り出せるようにしています。
個人のパソコンに保存するだけではなく、中央にあるファイルサーバーを利用することで、複数人で安全かつ効率的にデータを扱うことができます。
■データベースサーバー
大量の情報を整理して保存するためのサーバーです。
ECサイトの商品情報やユーザー情報、業務システムのデータなどをまとめて管理し、必要なときに検索・更新・取り出せるようにしています。
個人のパソコンだけでデータを管理するのではなく、データベースサーバーを利用することで、複数人が効率よく情報を共有し、正確に処理できるようになります。
■アプリケーションサーバー
プログラムを実際に動かすためのサーバーです。
Webサイトや業務アプリなど、ユーザーの操作に応じた計算や処理を行い、その結果を返します。
個々の端末だけで処理するのではなく、アプリケーションサーバーを利用することで、複数の利用者が同じサービスをスムーズに使えるようになります。
■認証サーバー
ユーザーのIDやパスワードを確認し、アクセス権を管理するサーバーです。
社内システムやクラウドサービスなどで、誰がどこまで利用できるかを管理します。
個人が自分だけでアクセス権を管理するのではなく、認証サーバーを利用することで、複数人が安全にサービスを利用できるようになります。
紹介した以外にも、バックアップサーバー、DNSサーバーなど、様々な機能を持ったサーバーが世の中では使われています。
それぞれのサーバーが、情報を整理・管理したり、複数の利用者に同時にサービスを提供したりすることで、私たちは日常的にインターネットや社内システム、オンラインサービスをスムーズに利用できるのです。
こうして見ると、サーバーは目立たない存在ながら、私たちの生活や仕事を支える縁の下の力持ちと言えるでしょう。

「Linux(リナックス)」はサーバーで使われるOS
多くのサーバーは Linux と呼ばれるOS(コンピューターを動かす基本ソフト)で動いています。
Linuxは安定性やセキュリティの高さから、企業やサービス提供者に広く使われています。
また、操作画面がWindowsと似ていて扱いやすい Windows Server も、企業の業務システムや社内サービスで広く利用されています。
用途や環境に応じて、LinuxとWindows Serverが使い分けられています。
さらに、最近では クラウドサーバー が一般的になっています。
一昔前は高性能なサーバーコンピューターを会社内に設置して、そこから利用者に向けてサービスを提供するやりかたが主流でした。
クラウドサーバーを使うと、物理的なサーバーコンピューターを自社で置かなくても、インターネット経由で必要なサービスやデータを利用できます。
これにより、企業は高価なコンピューターを購入したり維持したりする必要がないので、初期投資や運用の手間を抑えつつ、柔軟にサーバー環境を拡張することが可能です。
また、1台のサーバーの中で複数の独立した環境を作る 仮想サーバー の仕組みもよく使われます。
これを利用すると、同じ物理サーバー上でWebサーバーやメールサーバー、データベースサーバーなどを同時に動かすことができ、効率よく運用できます。
障害が起きても仮想環境を別のサーバーに移動させることで、サービスを止めずに対応できるのも大きな利点です。
世の中に必要不可欠なサーバーエンジニアのお仕事
こうしたサーバーを支えるのが、 運用・保守を担うサーバーエンジニアです。
運用・保守とは、サーバーが安定して動くように監視し、設定やリソースの調整を行うほか、トラブルや障害が起きたときに迅速に対応し、サーバーやサービスを復旧させる役割を持っています。
サーバーの設定や監視、トラブル対応、性能の最適化など、目に見えない部分で日々の業務を支えているのが彼らです。
もしサーバーが停止すれば、業務が止まり、サービス利用者にも大きな影響が出てしまいます。
だからこそ、サーバーを扱うエンジニアは、現代のIT社会を支える非常に重要な存在です。
私たちは普段意識することは少なくても、サーバーとそれを支えるエンジニアがいるからこそ、日常的にインターネットや業務システムをスムーズに利用できるのです。
そんな目立たないけど社会を縁の下で支える重要なサーバーエンジニアのお仕事、もし興味を持たれたらご自身でも深く調べてみてください。