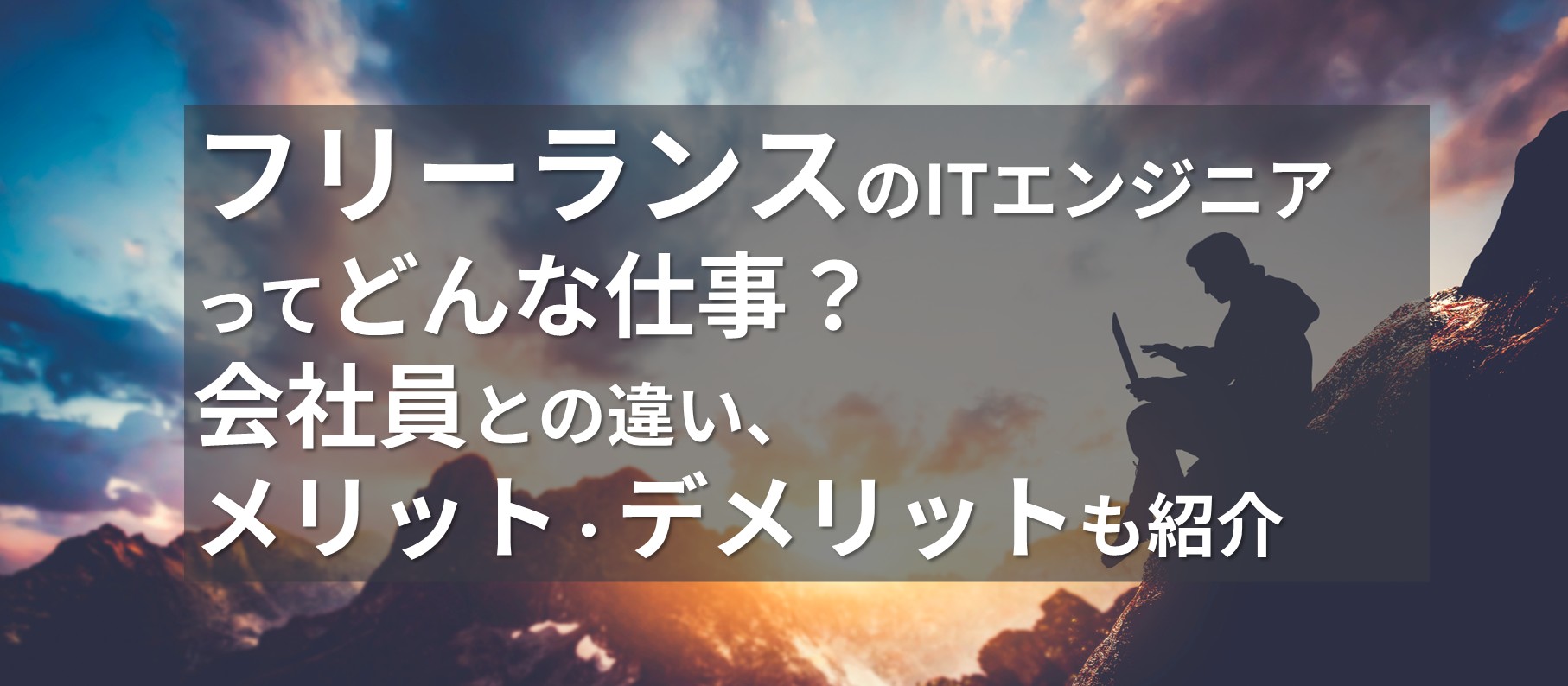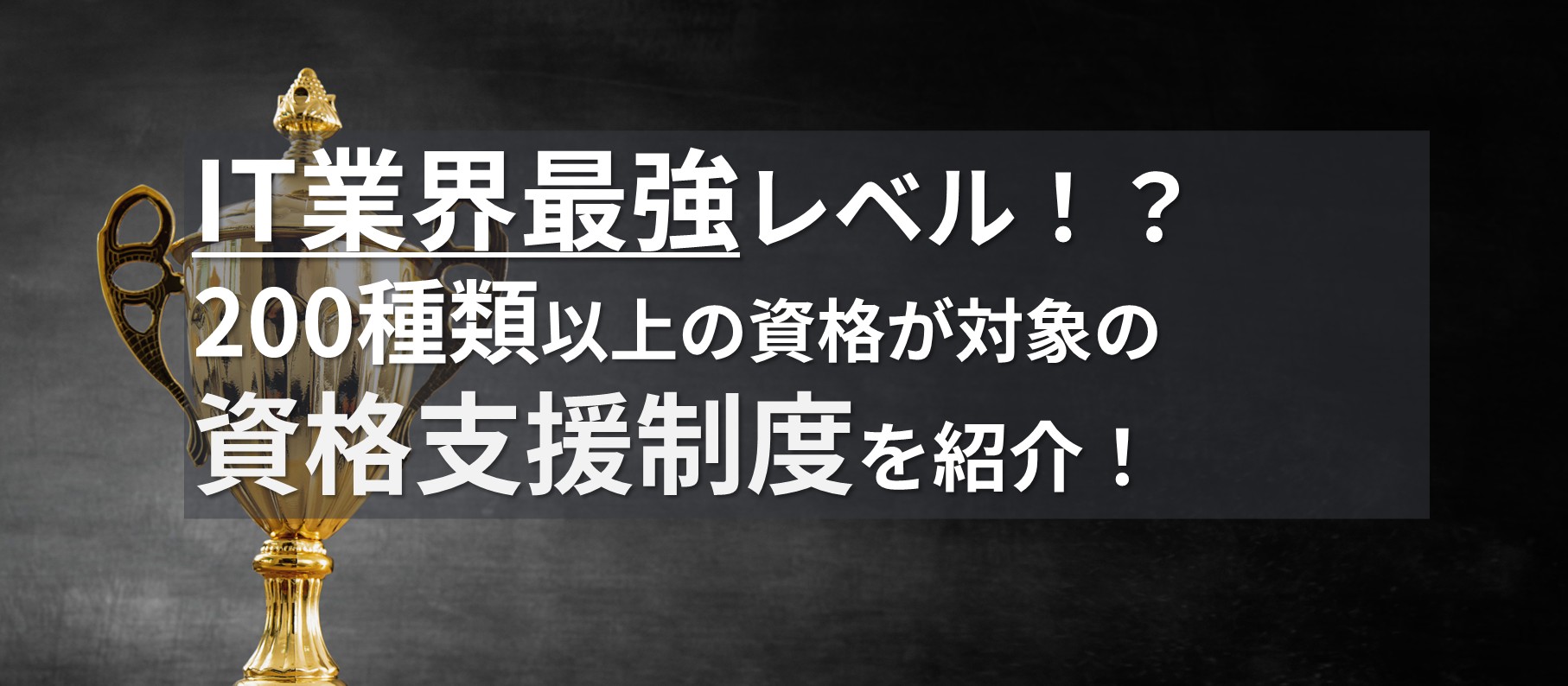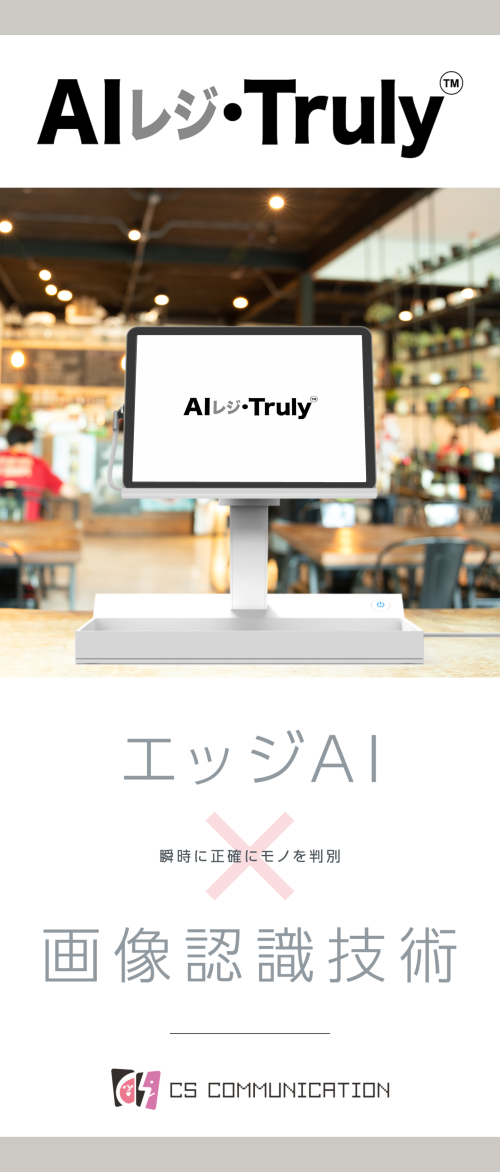フレックスタイム制度でどう変わった?効率的な働き方を導入した当社の事例
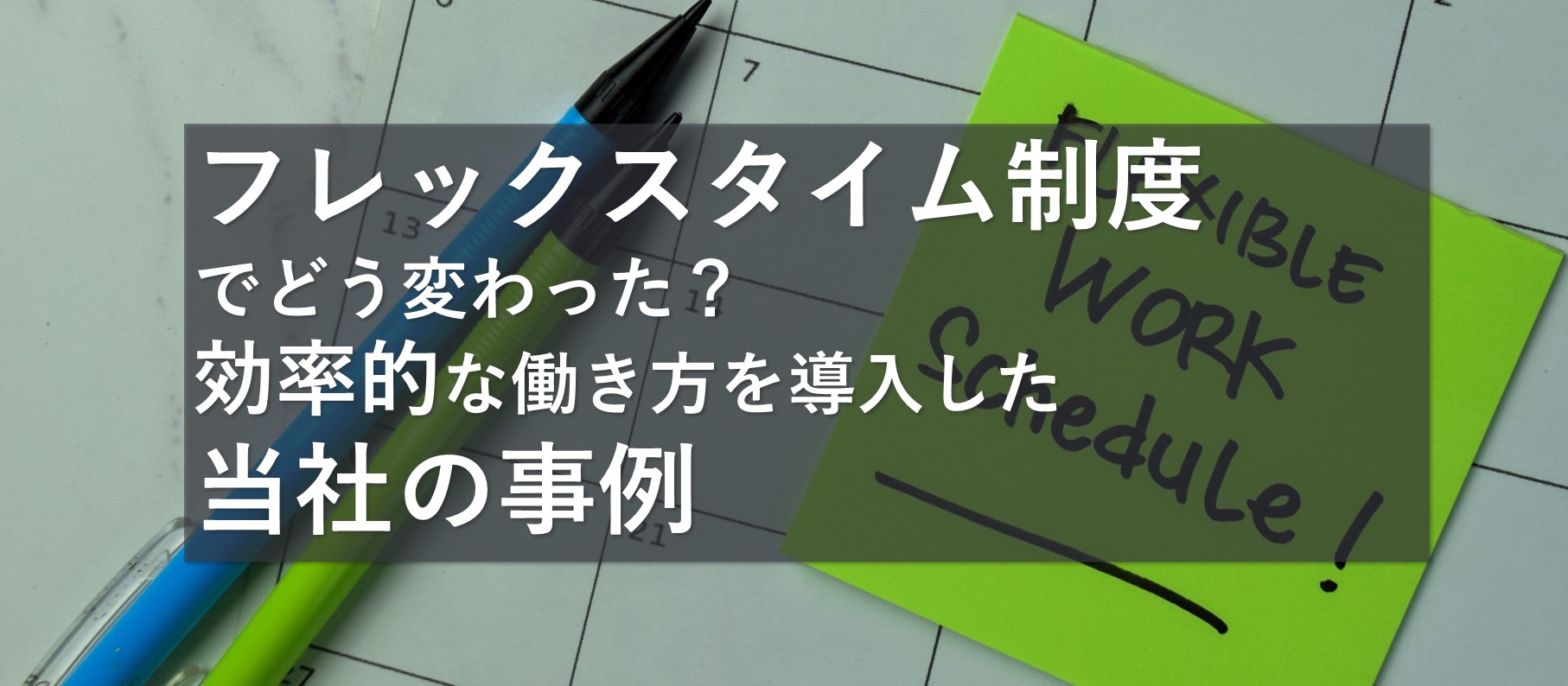
当社、シーエスコミュニケーションでも5年ほど前からフレックスタイム制度を取り入れており、今では社内に浸透してきたと感じています。
決まった時間で働くよりも、自由度が高いように感じるフレックスタイム制度ですが、従業員だけではなく会社にとってもメリットがある働き方だと言えます。
今回はフレックスタイム制度についての基本的な解説と、実際にIT業界でフレックスタイムで働くことの実態をお伝えします。

フレックスタイム制度とは?基本をわかりやすく解説
フレックスタイム制度とは、勤務時間を社員がある程度自由に決められる仕組みのことです。
今まで一般的だった定時勤務の企業では「9時に出社して18時に退社」といった固定の勤務時間が決められています。
一方、フレックス制度を導入している会社では、出社や退社の時刻を自分のライフスタイルに合わせて調整することができます。
たとえば、朝型の人なら午前7時に出社して午後4時に退社することも可能ですし、夜型の人なら午前11時に出社して午後8時まで働く、といった働き方もできます。
子育てや家事と両立したい人であれば、午前中は子どもの送迎をして昼前に出社し、夕方には一度退勤して、夜に自宅からリモートで残りの作業を進めるという形も取れます。
もちろん会社のルールやチームの状況に合わせる必要はありますが、このようにフレックスタイム制度は「一人ひとりに合った勤務スタイル」を可能にする仕組みなのです。
ただし会社の定めた一日の労働時間や一か月の所定労働時間はきちんと守る必要があり、短く働ける制度ではありません。
この制度には「コアタイム」と「フレキシブルタイム」という考え方があり、コアタイムは必ず勤務していなければならない時間帯、フレキシブルタイムは自由に出社や退社を選べる時間帯を指します。
会社によってはコアタイムを設けず、完全に自由に働ける「完全フレックス」を採用している場合もあります。
固定された勤務時間と比べると、通勤ラッシュを避けられたり、家庭の事情に合わせて働けたりと、自分の生活リズムに合った働き方ができるのが大きな特徴です。
つまりフレックスタイム制度は、従来のように一律に決められた時間に働くのではなく、一人ひとりの都合や生活スタイルに合わせて柔軟に調整できる仕組みだと言えます。
IT業界におけるフレックス勤務のメリット
IT業界でフレックスタイム制度が広く導入されているのは、単に働きやすさのためだけではありません。
エンジニアやデザイナーといったクリエイティブ職種にとって、生産性を高めやすい働き方だからです。
開発業務は集中力が求められる場面が多く、必ずしも決まった時間帯にパフォーマンスを発揮できるとは限りません。
フレックス制度を取り入れることで、自分が最も集中できる時間帯に作業を進められるため、効率性の向上につながります。
また、人によって生活リズムは大きく異なります。
朝早くから頭が冴えて作業がはかどる人もいれば、夜になってから集中力が高まる人もいます。
固定された勤務時間ではその個性を活かしきれませんが、フレックスタイム制度があれば朝型や夜型といった違いを尊重しながら、自分に合ったスタイルで働くことができます。
結果として、社員が無理なく力を発揮できる環境が整うのです。
さらに大きなメリットとして、通勤混雑を避けられる点があります。
出社時間を調整できるため、満員電車のピークを外して快適に通勤でき、その分ストレスも軽減されます。
余裕ができた時間を活用して、資格の勉強や自己学習にあてる人も少なくありません。
IT業界では新しい技術を学び続けることが重要ですが、フレックスタイム制度はその学習時間を確保しやすい環境を提供してくれます。
ただし、ITエンジニアといっても仕事の内容は多様です。
システムの保守や運用、夜間に稼働するサーバー管理など、チーム全体のスケジュールに合わせる必要がある業務では、フレックスタイムの柔軟性を活かしにくい場合があります。
一方、開発や設計、クリエイティブな業務のように、個々の作業ペースで進められる仕事では、フレックスタイム制度を最大限に活かすことができます。
つまり、制度のメリットは「仕事の性質」によって大きく変わるため、自分の担当する業務と照らし合わせてイメージすることが重要です。
シーエスコミュニケーションのフレックスタイム制度
当社のフレックスタイム制度は、世の中が新型コロナウイルスの影響で大きく揺れ始めた2020年4月に導入されました。
リモートワークと組み合わせることで、パンデミックに対応した柔軟な働き方をいち早く取り入れ、感染リスクを最小限に抑えることができました。
制度の内容は、平日の11:00〜15:00をコアタイムとし、6:00〜11:00と15:00〜22:00がフレキシブルタイムとなります。
月の出勤日数に8時間を掛けた時間が所定労働時間となり、これを下回ると給与から控除が発生し、上回った分は残業代として支給されます。
実際に社内では、出勤時間をずらすことで首都圏の満員電車を避けている社員が多くいます。
また、家庭の都合で夕方に一度退勤し、夜に再度数時間働くといった柔軟な働き方をしている社員もいます。
一方で、フレックスタイムを利用しつつも、従来通り9:00〜18:00で働いている社員も少なくありません。
私自身も業務上の都合(部下との出勤調整など)から基本的には9:00〜18:00勤務をしていますが、必要に応じて午前中に病院へ行ったり、私用で16時に退勤したりと、フレックスの恩恵を受けています。
残業が多くなった月には、調整が可能なタイミングで早めに退勤し、買い物や友人との食事に充てることもあります。
制度のおかげで、業務だけでなくプライベートの予定にも柔軟性を持たせられるようになりました。
ただし、すべてのエンジニアがこの制度を自由に使えるわけではありません。
案件によって勤務時間が固定される場合や、シフト制で働いているメンバーもいるため、職種や業務内容に応じて利用の仕方はさまざまです。
フレックスタイム制度で実現する新しい働き方
ITエンジニアは技術を身につけてキャリアを築いていけば、こうしたフレックスタイム制度をはじめとした柔軟な働き方を自ら選べるようになります。
働き方に縛られるのではなく、自分のスキルによって選択肢を広げられることこそ、ITエンジニアという職業の大きな魅力のひとつと言えるでしょう。
フレックスタイム制度の大きな魅力は、単に「働く時間を選べる」というだけではなく、人生そのものの質を高められる点にあります。
自分の生活リズムや家庭の事情に合わせて働けることで、心身の負担が減り、ワークライフバランスが向上します。
仕事と生活の境界が心地よく整うことで、長期的に健やかにキャリアを積んでいける環境が整うのです。
また、IT業界では常に新しい技術や知識を吸収していくことが求められます。
フレックスタイム制度を活用すれば、通勤時間を避けて確保できた余裕のある時間を、資格取得や自己学習に充てることも可能です。
自分のペースで学び、実務に活かしていくサイクルを回せることは、キャリア形成において大きな武器となります。
このような自由度の高い働き方は、これからの時代にますます必要とされていくでしょう。
場所や時間にとらわれず、自分に合った形で力を発揮できる環境は、働く人にとっても企業にとっても大きな価値があります。
柔軟な制度を活用しながら、自分のライフスタイルに合ったキャリアを築いていきたいと考える人にとって、フレックスタイム制度は大きな可能性を広げてくれるはずです。
当社も、この制度を活かしながら社員一人ひとりがより働きやすい環境を整え、挑戦と成長を後押ししていきたいと考えています。
フレックスタイムをはじめとした柔軟な制度を通して、これからもエンジニアが安心して力を発揮できる会社づくりを進めてまいります。