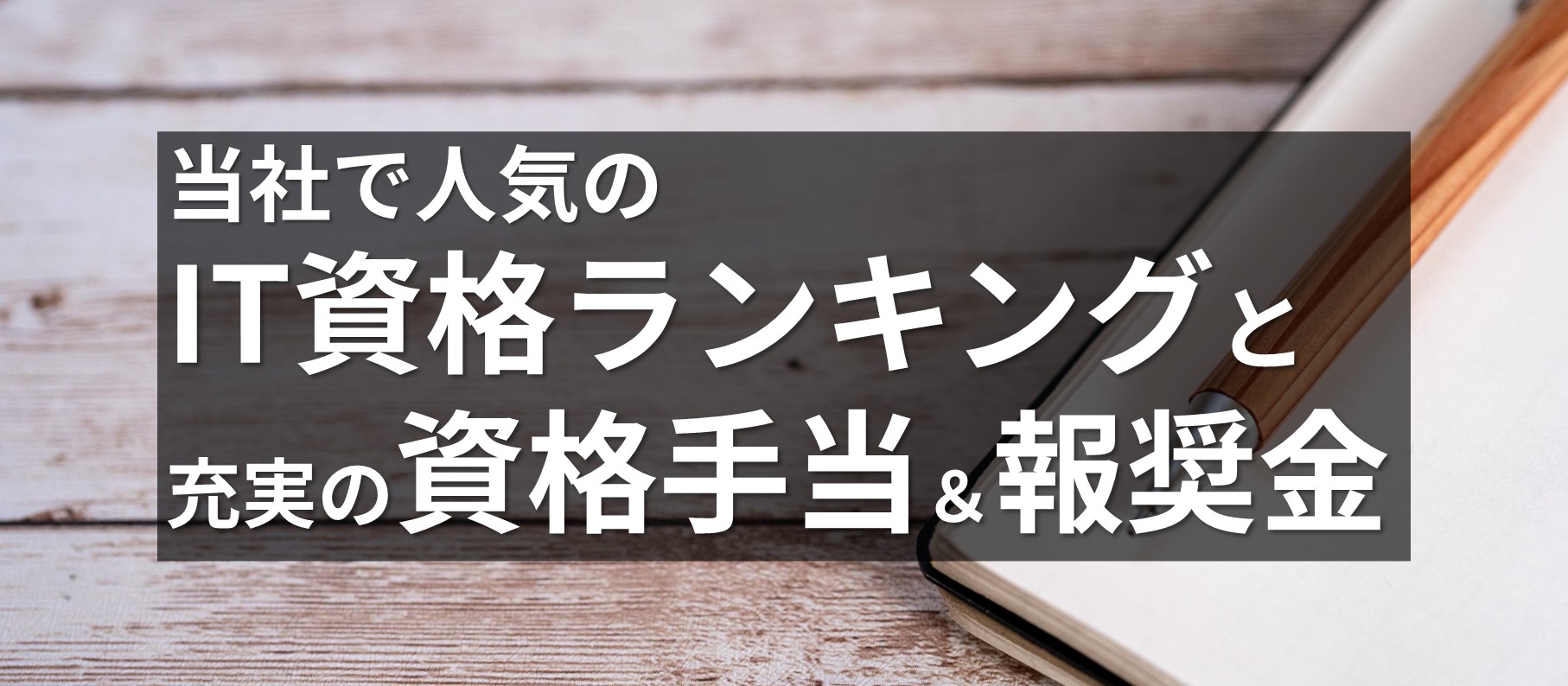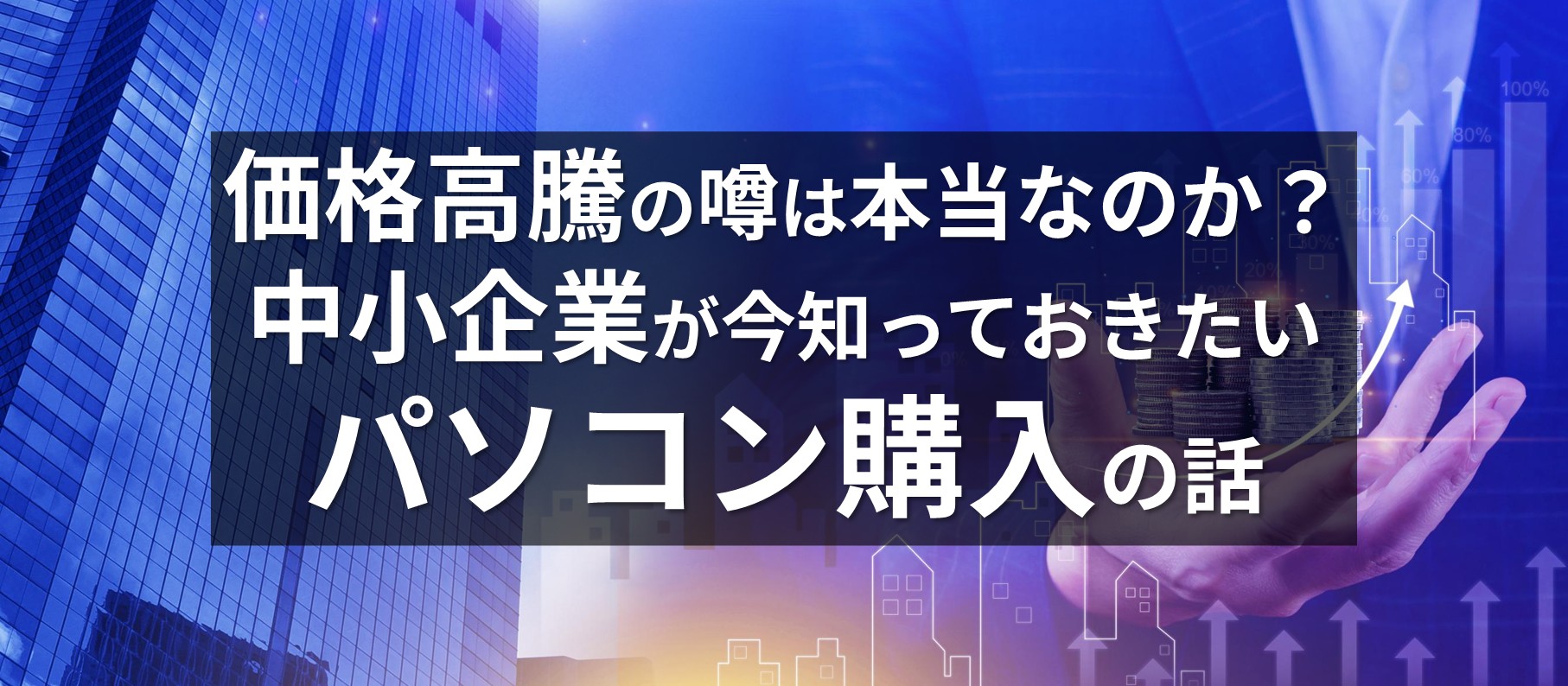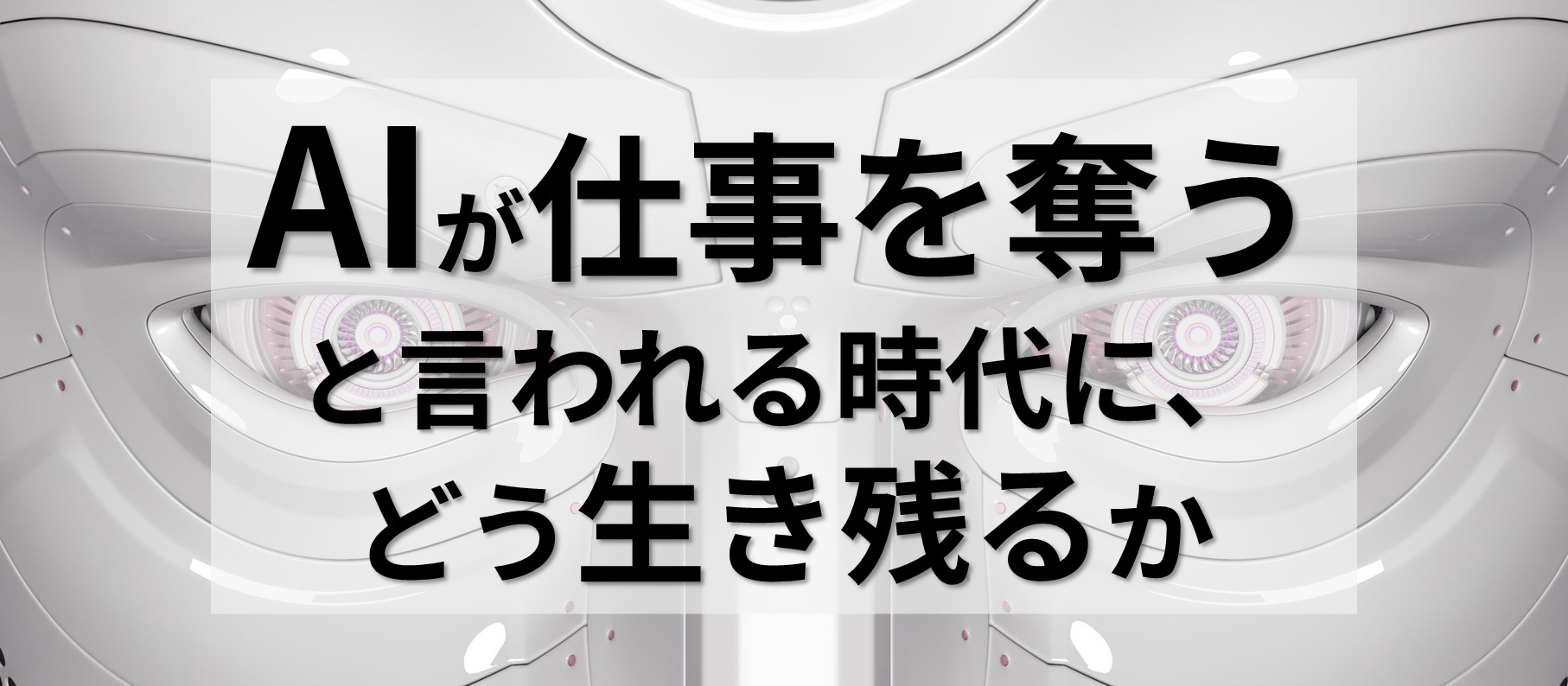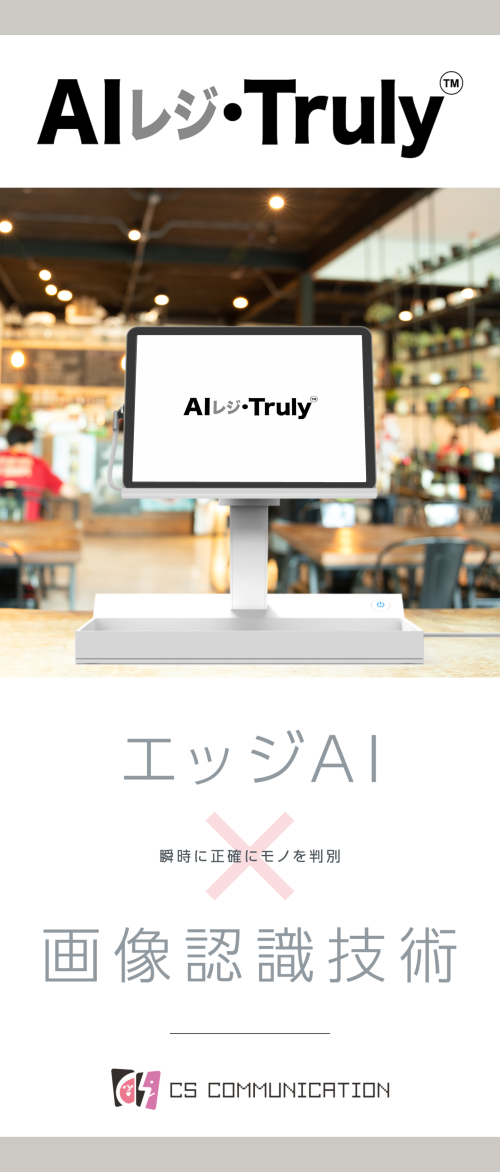ITエンジニアとして新社会人になるのが不安なキミへ
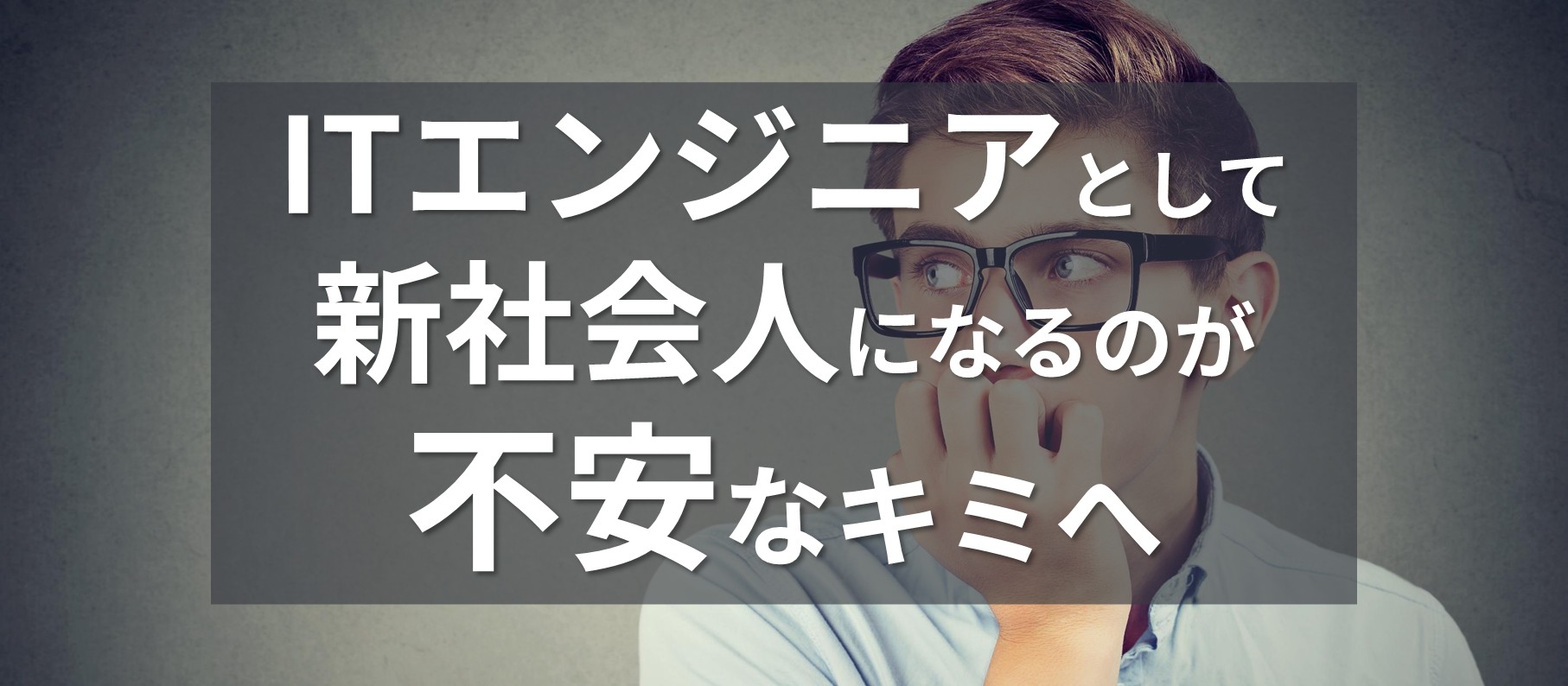
技術を仕事にできることにワクワクする一方で、「本当に現場で通用するのだろうか」と不安もあると思います。
多くの人が入社前に資格やプログラミングの勉強を進めますが、実はそれだけでは十分ではありません。
会社の仲間やお客様と一緒に働き、仕事としてお給料をもらうために求められるものは、技術的なスキルだけではないのです。
では入社までの間にどんなことに取り組めば良いのでしょうか?
この数か月をどう過ごすかで、あなたが入社後に活躍できるかが大きく変わります。
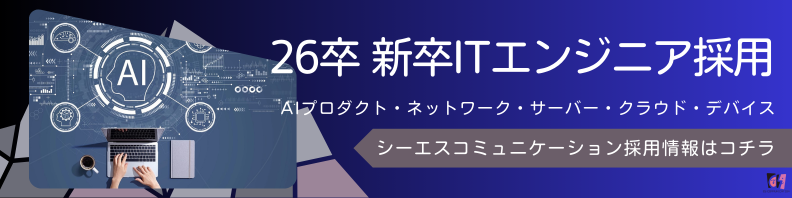
4月までに磨いておきたい、“仕事の基礎力”
ITエンジニアの仕事というと、プログラムを書く・ネットワークを設計するなど、技術のイメージが先に浮かびます。
けれど、現場で活躍するためには、社会人としての土台が欠かせません。
4月までに身につけておくと確実に役立つ5つのビジネススキルを紹介します。
1.基本的なPCスキル
Excel(関数・フィルター・ショートカット)やWord、メール、ファイル管理などのPC操作、基本的なパソコンに関するスキルは思っている以上に重要です。
なぜなら、入社直後に任されるのは、資料作成やデータ整理といった「派生する仕事」がとても多いからです。
Excelの操作スピードや表の整え方一つで、作業効率も印象も大きく変わります。
また、ファイル名の付け方やフォルダ整理も、“情報共有のセンス”として評価されます。
地味に見えても、こうした基本ができる人ほど、早く信頼を得て重要な仕事を任されるようになります。
2.報連相(ほうれんそう)の練習
報告・連絡・相談ができる人は、どんな現場でも重宝されます。
なぜなら、エンジニアの仕事は企業や組織に対して提供されるものが大半で、それらは一人で完結させることなどできないからです。
他のメンバーやお客様と情報を共有し、状況を合わせながら進める必要があります。
報連相がうまくいかないと、作業の重複や認識違いが起こり、結果的にプロジェクト全体の損失になります。
逆に、正確な報連相ができる人は、「信頼できる=一緒に仕事がしやすい」と評価されます。
入社前から、アルバイトやゼミで「結論から話す」「5W1Hで伝える」「伝えるべきことを整理してから伝える」といった練習をしてみてください。
伝え方を意識するだけで、周囲との関係がスムーズになり、チームに馴染むことができるようになります。
3.スケジュール管理・時間意識
社会人にとって、「時間・約束を守る」は最もシンプルで、最も大切な信頼の証です。
ITエンジニアの現場では、納期の1日遅れがシステム全体の遅延につながることもあります。
学生時代は自分のペースで進めても問題ありませんが、仕事ではあなたのスケジュールが他の誰かの仕事に直結します。
そのため、“締切を守る”はもちろん、“計画的に進める”という意識を持つことが大切です。
何らかのトラブルが発生することも想定して、余裕のあるスケジュールを設定しておくことも必要となります。
Googleカレンダーやタスク管理アプリなどを使って、自分の時間を“見える化”してみましょう。
「自分の時間を管理できる人」は、社会人として最初の信頼を得られる人です。
4.敬語・ビジネスマナー
ビジネスマナーとは、ただの形式ではなく、“信頼を築くための言語”です。
たとえば、チャットやメールでの言葉遣い一つで、「この人と仕事がしやすい」と感じてもらえるかどうかが変わります。
お客様だけでなく、社内の上司や先輩への敬意を言葉で表現できる人は、円滑なコミュニケーションが取れます。
それは結果的に、仕事のスピードを上げることにもつながります。
また、服装や身だしなみも同じです。
「誰にどう見られても恥ずかしくない状態でいる」ことは、プロとしての基本です。
社会では「何ができるか」よりも、「誰に任せたいか」が信頼によって決まります。
ビジネスマナーは「自分の信頼度を底上げしてくれる土台」となるため、早い段階から身につけることに意味があります。
5.学び続ける姿勢
IT業界は、1年前の知識がすでに古くなるほど変化の速い世界です。
だからこそ、“自分で調べる習慣”が欠かせません。
わからないことをすぐに人に聞くより、まずは自分で調べてみる。
試して、考えて、それでも解決できなかったら質問する。
この流れを身につけておくと、入社後の成長スピードが段違いになります。
「受け取る学び」から「自分で探す学び」へ。
それが、エンジニアとして成長を続けるための第一歩です。
技術スキルよりも先に身につけてほしいのは、信頼される人としての土台です。
どんなに優れたスキルを持っていても、信頼されなければ仕事は任せてもらえません。
今回紹介した5つの要素は、学生のうちから身につけられるものですし、既に今までの経験から身につけている人もいるかと思います。
時間がある今だから、広い世界に飛び出そう!
ITエンジニアの仕事に必要なのは、技術だけではありません。
実際に多くの現場を見ていると、早く成長する人ほど社会をよく観察し、人と関わり、自分で動いた経験を持っています。
エンジニアの価値は、「何を知っているか」よりも、「どう考え、どう行動できるか」で決まります。
その力は、教室や本の中ではなく、現実の経験の中でしか磨けません。
では、どんな経験をしておくといいのでしょうか。一例を紹介します。
1.一人旅をしてみる ― 判断力と適応力を鍛える
一人旅は、最もシンプルで最も実践的な“問題解決トレーニング”です。
行き先を決め、交通手段を調べ、トラブルが起きたら自分で判断して動く。
この一連の流れは、エンジニアの仕事に直結します。
たとえば、想定外の電車遅延やホテルのトラブル。
そのときに「誰のせいか」を探すのではなく、「今できる最善策は何か」を考える。
まさにそれが、現場で求められる“課題解決思考”です。
ITの現場では、想定外のことが日常的に起こります。
一人旅を通して身につく判断力・冷静さ・柔軟性は、技術スキルよりも貴重な武器になります。
言葉や文化の異なる海外であれば、更に広い世界を知るための経験になるでしょう。
2.アルバイトなどで様々な人と関わる―より多様な人とチームを組む
社会に出ると、仕事は必ず「人との関わり」で成り立ちます。
バイト先の上司・同僚・お客様。年齢も立場も考え方も違う人たちと関わる中で、相手の立場に立って動く力が磨かれます。
たとえば飲食店のアルバイトでは、急な注文変更やクレーム対応など、予期せぬ出来事が多くあります。
それをどう受け止め、どう対応するか。
その中で自然と「相手の意図をくみ取る力」や「感情を整える力」「チームで成果を出す」意識が身につきます。
既にアルバイトをしている方は、他の業種や職種のアルバイトにチャレンジして、新しい環境を求めるのもいいと思います。
3.ニュース・本・芸術に触れる ― 視野を広げ、感性を磨く
エンジニアの仕事は、技術的な正確さだけでなく、人にとって心地よい仕組みを作ることでもあります。
そのためには、社会の流れや多様な価値観を知ることが欠かせません。
たとえばニュースを見て、なぜこのサービスが流行っているのかを考えたり、戦争や紛争が起きてしまう背景を学ぶ。
アートや音楽に触れて、「人が何に心を動かされるのか」を感じる。
そうした体験が、システムの設計やユーザー体験の発想につながります。
“感性”と聞くと抽象的に感じるかもしれませんが、社会を観察し、人の感情を理解する力こそ、創造的なエンジニアに必要な素養です。
この感性はどうしても年齢とともに硬化してしまうので、若いうちから磨き育てていくべきでしょう。
机の上で学んだ知識は、現場での経験によって初めて「血の通った技術」になります。
一人旅の判断力、人との関わりで得る調整力、文化や社会を知ることで生まれる想像力。
それらは、どんなプログラミング言語にも勝る“人間力”です。
社会を知れば、なぜ技術が必要なのかが見えてきます。
そして、その理解こそがエンジニアとしての成長を一段上のレベルに引き上げてくれるのです。
AIに淘汰されないエンジニアになるために
エンジニアにとって、スキルを磨くことは確かに大切です。
でも、そのスキルを「どこで・誰のために使うのか」が見えていなければ、技術はただの知識で終わってしまいます。
社会人とは、“求められる側”として応える人。
そして、エンジニアとは、“誰かの課題を技術で解決する人”です。
そのために必要なのは、まず社会を理解する目線を持つこと。
それを育てるのが、いまのあなたに残された「入社までの時間」です。
いまのうちに、“世界を広げる経験”をしてほしい
4月までの数か月は、自由に使える貴重な時間です。
仕事が始まれば、旅に出たり、長期でなにかに取り組むことは簡単ではありません。
今のうちに、できるだけたくさんの「初めて」に出会ってください。
見たことのない場所に行き、知らない人と話し、価値観の違いに触れる。
たとえば旅先で感じた不便さや、人とのやり取りで得た気づきは、“課題発見の感性”を育てます。
そうした経験は、将来システムを設計するときや、お客様と向き合うときに確実に活きてきます。
なぜならば、エンジニアが設計する仕組みは、最終的には「人を幸せにする」ためのものだからです。
スキルはあとからでも身につけられる
多くの人が「入社前にスキルを磨かないと不安」と感じます。
でも、人事の立場から見ても、技術は入社後でも十分に追いつけます。
むしろ、最初から完璧にできる人はいません。
大事なのは、“学び続けられる姿勢”と“素直に吸収する柔軟さ”。
この2つがある人は、どんな環境でも確実に伸びていきます。
逆に、スキルだけに偏ると、社会や人との関わりに鈍感になってしまいがちです。
“上手にコードを書く人”ではなく、“技術を使って人を動かせる人”になること。
それが、これからの時代のエンジニアに求められる姿です。
AIにはできない、人間だけの力を育てよう
AIの進化は目覚ましいです。
コードを書く、テストを自動化するといった作業は、今後どんどんAIに代替されていくでしょう。
けれど、AIにはできないことがあります。
それは、「人の気持ちを理解し、共感し、言葉を選ぶこと」。
そして、「不確実な状況で、最善を選び取る判断をすること」です。
この“人間力”こそが、これからのITエンジニアの価値になります。
広い世界を知り、多くの人と関わり、自分の中に経験を蓄えること。
それがあなたを、AIには真似できない市場価値の高いエンジニアにしてくれるのです。
ITスキルを「車」、人生経験を「地図」と例えるとわかりやすいのではないでしょうか。
高性能な車であれば速く遠くまで走れますが、地図がなければ、どこへ向かえばいいのか分かりません。
一方で、詳細な地図があれば、自分の目的地を選び、どんな道を通るかを判断できます。
人生経験を積むことで、道の高低差や渋滞情報まで知れ、より快適な旅ができるようになるでしょう。
技術だけで走り続ける人は、いつか迷子になります。
経験という地図を手に入れた人だけが、自分の意思で進む方向を選ぶことができ、それはAIには真似できないあなただけの強みになります。
4月に社会へ出るその日まで、どうか「自分の地図」を描く時間を大切にしてください。
新しい場所に行き、人と話し、知らないことに触れる。
その一つひとつが、あなたの技術を“本当に人の役に立つ力”へと変えていきます。
広い世界を知ること。それが、エンジニアとしての最初の成長です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。